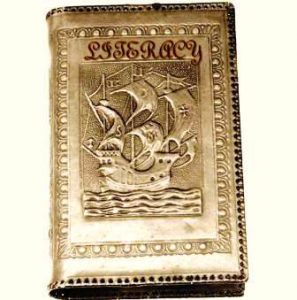池波正太郎『男の作法』の書評、最後は知性と生き方のことをアラカルト風に。
本とメモ 企画術や仕事術の話をした後に、受講生から読書の方法についてよく聞かれる。義務教育で教えられていないから、いい歳になって他人に聞く。「好きなものを好きなだけ読んで自分流の読書をすればいい」と伝える。そっけない返事だが、それ以上でもそれ以下でもない。読むべき本を推薦するなどもってのほかである。
「本を読むのは千差万別ですよ。あらゆるものを読んでますよ。(……)本をたくさん読んでいくうちにね、おのずから読みかたというものが会得できるんですよ。」
この通りであり、これしかない。ぼくの経験から言うと、十代・二十代のある時期に二、三年間手当り次第に数百冊を読めばだいたいわかってくる。やがて趣味や仕事が明確に絞られるようになると、何をどう読むべきかがおのずから見えてくる。読書の質を云々する前に、かなりの冊数を読破せねばならない。中年には手遅れで申し訳ない処方箋だが……。
メモについてはさほど熱心ではなく怠け者だと池波は言うが、やったほうがいいと勧める。メモやノートの類いは単なる備忘録ではなく、文字を連ねることによる知の劣化防止だ。覚えようとしなくても、自ら書いた文章を読み返せば記憶が再生される。最近ぼくは覚えることよりも、覚えたことを思い出すことに意義を見出すようになった。「愛読書は?」と聞かれたら、躊躇せずに「ぼくの書いたノートやブログ」と答える。
小道具 若い頃から万年筆に憧れていた。大した稼ぎもないのに、なけなしの金をはたいて買っていた。一本あれば十分なのに、店頭で見るたびに垂涎の思いに駆られたものだ。それほど万年筆には愛着があるので常時使うようにしている。だから、次の考えに異論はない。
「万年筆だけは、いくら高級なものを持っていてもいい。(……)そりゃあ万年筆というのは、(……)男の武器だからねえ。(……)高い時計をしてるより、高い万年筆を持っているほうが、そりゃキリッとしますよ。」

時計と万年筆なら万年筆に決まっている。池波の言う「高級」は五万や十万やそれ以上の値段のことだから、誰にでも当てはまるものではない。数千円から十万円超の万年筆を各種持っているが、高級であることと書き味、握り具合、見た目は比例しない。インクや紙や、もっと言えば、字の巧拙も関係する。使わずに見せびらかすだけの高級な万年筆が武器になるはずもない。長年使い込み、しかもよく手入れをしている万年筆が値打ちを漂わせるのである。革の手帳にも同じことが言えると思う。
生き様
「他人の休日に働き、他人が働いているときに休む……というのが、ぼくの流儀なんだ。」
ぼくがサラリーマンを辞めた理由の一つがこれだった。仕事の中に、ほんの少しでもいいからマイペースと自分流が欲しかった。生き様というのは個人が決めるもの。混雑や群れを避けて一人のプライムタイムを持つのは固有の生き様にとって必然である。
「他人に時間の上において迷惑をかけることは非常に恥ずべきことなんだ。(……)自分は何をやったっていい。だけど他人との接触においては一人の社会人としてふるまわなければならないわけだ。」
その通りである。約束は守るべし。半時間待たされるということは半時間失うことに等しい。不可抗力で約束を破らざるをえなくなったり遅刻したりしても言い訳をせず、詫びて謝るのが作法である。
「現代の若い人たちを見ていて感じることは、(……)プロセスによって自分を鍛えていこうとか、プロセスによって自分がいろんなもんを得ようということがない。」
またまた同意する。結果主義の時代、人はつまらなくなってしまった。プロセスが鍛錬の場でありゴールそのものであるケースは稀ではない。旅などはまさしくそれだろう。旅先よりも旅路そのものに意義がある。
「どんな仕事だって(……)努力だけじゃ駄目なんだ(……)一種のスポーツのように楽しむ。」
一所懸命は愉快だからできるわけであって、愉快のない仕事は長続きしない。仕事にコミットすること自体が楽しくなくてはいけない。ぼくの仕事はワークシェアとあまり縁がなく、たいていのことは自分に始まり自分で完結する。孤独であり厳しいが、自助自力でする仕事の楽しみは格別である。
さて、池波作法のあるものはアンチテーゼ、別のものはアマノジャクのように響くかもしれない。この本が書かれてから四十年以上経った今、無粋にして男気のない男どもがいっそう増えたからにほかならない。