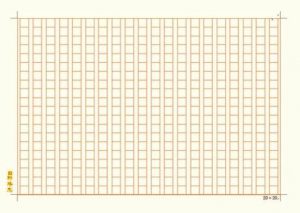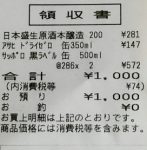一回り年上のYさんのことについては、このブログで何度か書いている(直近では「全機透脱」)。ぼくのようななまくら雑学の輩とは違い、深読みの読書家だった。還暦を過ぎてからはもっぱらシェークスピアと小林秀雄とドストエフスキーに傾倒されていた。
年に一度会えるか会えないかという関係だったが、その一度はたいてい喫茶店での読書談義だった。二時間以上話し込むことも稀ではなかった。「役に立つ本を読まず、読みたい本を好奇心のおもむくまま読むあなたに刺激を受けて以来、古典と小林です」と言われた時は正直驚いた。Y氏の知的好奇心の足元に及ぶはずもないと思っていたからである。
知のオーラではなく、知的好奇心のオーラ。そういうオーラが出ている人に対しては、手抜きせずに感応するしかない。好奇心たくましい人は、相手が気づいていない潜在の知を上手に引き出してくれる。Y氏と話をするたびに、自分が自覚していなかった自分の考えに気づいてハッとさせられたものである。
「知的」と名の付く本をいくら読んでも、知的好奇心旺盛であることの証明にはならない。博覧強記的な知性のオーラなどは、知的好奇心が横溢するオーラの前では色褪せるのだ。最近、明けても暮れてもたわいもない昔話や世間話を持ち出す知人との付き合い方に戸惑うようになった。いや、無理して付き合う必要はないのだが、やむなく付き合うとなれば相手に合わせるしかない。
相手に合わせてもらっている人間が、今の器以上に大きくなるはずもない。やがてこちらも合わせるのが面倒だし、刺激を受けることもないので距離を置くようになる。歳相応の知的好奇心というものがあり、それが雑談の中身に関わってくる。知的好奇心が薄れると世間話しかできなくなる。やがて老化が進む。
Yさんは知をものにしようなどと思っていなかったはずだが、知的好奇心に溢れていた。こちらが息を抜けないようなオーラがあった。「難病を患っていた夫は七十九歳で旅立ちました」という書き出しの奥さまからの葉書の文面はこう続く。「亡くなる数日前にも、新しい書籍を求める等、最後まで意欲的に生きたと思います」。何という生の最期の密度であることか。