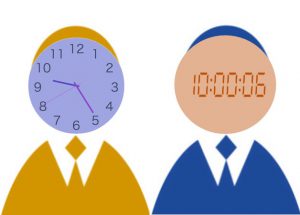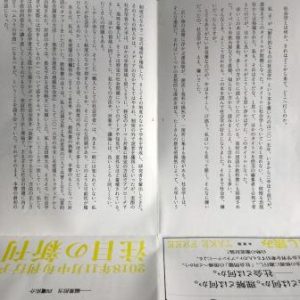正月に神社で梅の枝を見、その一ヵ月後に公園で梅の蕾を認めた。陽気が春めいてくると、梅の花がつつましやかに咲くのを見逃して、目線は華やかな桜へと移りがち。ここ数年こんな具合だ。
元日に訪れる高津宮の、ぼくなりの梅三題の筆頭は「梅ノ井」。大阪の府の花と言えば梅。大阪市中央区の区の花も梅。中央区の大阪城公園にも有名な梅林がある。江戸時代から高津宮一帯は梅の名所だった。今は微かな痕跡しかないが、当時は梅川という川がこのあたりを流れており、梅の井には上町台地の伏流水が湧いていた。井戸にしたほどだからかなりの名水だったらしい。現在の梅の井は石蓋で閉ざされた空井戸である。
梅川の微かな痕跡というのは、その川に架けられた「梅乃橋」。これが二題目。二百五十年前に奉納されたもので、今も残っている。梅川は東から西へ流れる川だった。この川の下流あたりを掘り下げて川幅を広げたのが今の道頓堀という説がある。この場所から道頓堀のグリコの電飾サインまでは直線で1.3キロメートル。見事に真っ直ぐ西方向。
三題目は「献梅碑」。わが国に『論語』と『千字文』をもたらした王仁博士の歌を刻んだ碑である。建立は90年前と比較的新しいが、エピソードは1600年前に遡る。昨日、梅花を神前に奉納する献梅祭が五日前に執り行われたと知った。祭は王仁博士が梅花に和歌を添えて仁徳天皇に奉ったことにちなむ。
難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花
あまりにも有名な一首がこれである。難波は今では「なんば」と呼ぶが、古代の大阪の呼び名は「なにわ」。
まもなく春べ、しかし「この花」の咲くのをまだ見ていない。オフィスから大阪城の梅林まではゆっくり歩いて半時間足らず。梅は五分咲きだという。週末に時間が取れれば行ってみようと思う。紅梅混じってこその梅林だが、どちらかと言うと、白梅びいきである。白梅の校章のついた学生帽をかぶって三年間高校に通ったせいかもしれない。