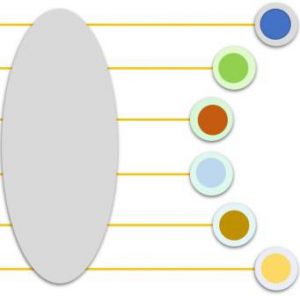「四十にして惑わず」と孔子は言った。惑わないためにはぶれない考え方が必要。そのためには記憶力の減退、知の衰えに抗わなければならない。少なくとも遅らせたい。さて、どう対処するか?
➀ 惑っていない振りをする。
➁ イチョウ葉エキスを飲む。
➂ 読み・書きを習慣とする。
➀で凌げば多少なりとも気休めになるかもしれない。格下相手なら振りが通用することもある。ただ、抜本的処方になりそうもない。それどころか、知のアンチエイジングが手遅れになりかねない。
商売柄、サプリメント販売業者は当然➁を推す。なにしろイチョウは地球上で最も経験豊富な植物なのである。たかだか数万年のキャリアしかないホモサピエンスに対して、イチョウは約2億5,000万年間、生き延びてきたのだ。
イチョウの葉のエキスには血管を広げる作用がある(らしい)。だから、動脈硬化を防ぐ(らしい)。血流が改善されると脳の毛細血管の血行がよくなる(らしい)から、認知症の改善に効果がある(らしい)。頭に血が流れたら記憶力が活発になり集中力も増す(らしい)。イチョウ葉はいいことづくめである(らしい)。もしこれらすべての「らしい」が確実であることが証明されれば、➁は絶対的に有力な対処法になる。
しかし、イチョウ葉エキスは定期購入すると毎月数千円、年に少なくとも5、6万円の出費になる。働き盛りの四十代ならともかく、仕事をしていないシニアにとっては家計の負担になる。そこで、➂という選択肢を真剣に検討することになる。
まず、買ったもののろくに読みもしていない手持ちの本を引っ張り出す。関心のあるテーマで、読みやすそうな本でいい。同じ本を何度も読み、気が向けば音読してみる。脳の血行がよくなり、記憶力も集中力も増す。慣れてくれば、読みながら傍線を引く。気になるページの欄外にメモを書き、少々面倒だが、ノートに転記すれば考えるきっかけにもなる。
ノートは数百円も出せばそこそこいいものが手に入る。そこに日々の気づきを書き込み、気まぐれに読み返せば個々のページに書いた情報どうしが相互に響き合い、気がつけば、考えることが常態になってくる。イチョウ葉と同じく「らしい」の域を出ない知のスローエイジング処方だが、イチョウ葉よりも財布にやさしいことは間違いない。