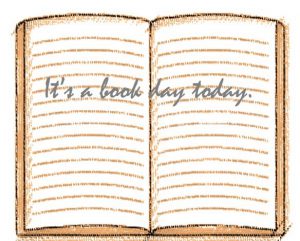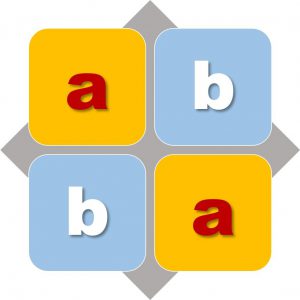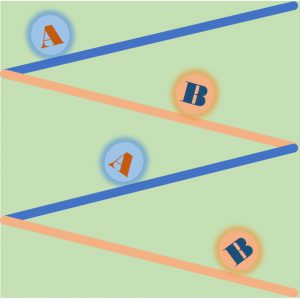二年前、オフィスの図書室兼勉強部屋を“Spin_off”と命名したが、実は別案があった。「本にちカフェ」というのがそれ。「本の日」と「本日」を重ねたもので、“It’s a book day today.”という英語のキャッチフレーズを作り、ドアの表示のデザインまで考えた。「本日は晴天なり」を捩って「本日は本の日なり」と訳せるかもしれない。
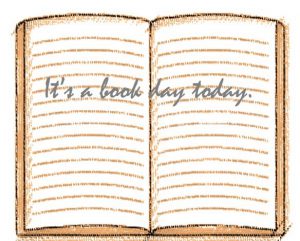
まとまった時間が作れたので、本を拾い読みしたり、主宰していた会読会のためにしたためた書評を読んだりしている。「本日は本の日なり」にふさわしそうな『読書のすすめ』(岩波文庫編集部編)の書評に新たに手を加えてみた。この本では37人の著名人がそれぞれ独自の読書論を寄稿している。そのうち18人を選び、今回と次回で9人ずつ紹介したいと思う。
ところで、最上の読書は、好きな本を好きな時に好きな姿勢で好きなページ数だけ愉しむのがいいということに尽きる。この歳になって、「いかに本を読むか」で悩むことはない。けれども、「読書家らはどんなふうに読んだのか」には少々興味があるので、時々覗いてみる。誰もが生活環境やキャリアによっていろいろな読み方をしていることがわかるが、少なからぬ共通項があることにも気づく。
📖 『ガリア戦記』からの出発(阿部謹也)
著者は現在をどのように生きるかと真剣に問い、生きるために不可欠なテーマを見つけようとするが、容易に見つからない。
「長い間考えたあげく、ついに何も考えず、何も読まずに生きてゆけるかどうかを考えてみた」。
そしてそれが不可能だとわかった。出合った一冊の本はカエサルの『ガリア戦記』だった。ぼくに「それを読まなければ生きてゆけない本」という選び方ができるだろうか。ちなみに、カエサルの『ガリア戦記』は本棚にあるが、なまくら読みしかしていない。
📖 読むことと想像すること(池内了)
「私にとって読書とは、それまでに未知であった世界を、想像しあるいは空想し、時には一体となって考えあるいは反発し、やがて既知の世界として私の中に沈めてゆく行為である。従って、たとえ実際に経験しない事柄でも、読むことと想像することによって限りなく近づき、私の中の世界の一事象とすることができると考えている。」
未知の世界のことを読むには辛抱がいる。知っていることを手掛かりにして知らないことに想像を馳せるわけだから。わからないという度々の状態に陥るのが嫌なら、読書を続けることはできないだろう。
📖 古典の習慣(大江健三郎)
「本を読むこと、とくに古典を読むことには、無意識的なものもふくめて全人格が参加している。それはひとりの人間の生きる上での習慣ともいえるものだ。」
全人格などと大それたことを言える自信はないが、読書が国語力だけで何とかなるなどとは思わない。歯を磨くことにしても、歯ブラシと歯磨剤だけで済むものではないのと同じことである。
📖 読書家・読書人になれない者の読書論(大岡信)
「本を読むという行為は、いついかなる場合においても、作者対読者の一対一の関係に還元されてしまう。」
「私たちは本を読む場合、必ずしも一冊全部を初めから終りまで読み通すとは限らない。ある場合には、ある本の一、二ページしか読まないこともある。そしてその一、二ページが、決定的に重要なことさえ多いのである。」
作者と読者の一対一の関係なのに、一冊を読み通さなくてもよく、一部齧るだけでもいいと言われれば安心する。ここが読書のいいところだ。もっとも、小説は別にして、たいていの本のテーマはもとより1ページか2ページで書けることが多いから、運よく開けたページが「さわり」であることなきにしもあらず。
📖 研究と読書(大野晋)
「読書とは眼鏡をかけて物を見るようなものである。多読家とは要するに次々と眼鏡をかけかえて行く人。眼は疲れて実は何もよく見えなくなるだろう。」
読まないよりは読むほうがいい。しかし、読まずに済ませる選択肢もある。いろいろと本を読んでも開眼するとはかぎらない。読書に親しむのはいいが、適度な距離を保つことも重要である。
📖 翻訳古典文学始末(加藤周一)
「私は日本語の美しさを、専ら本を読むことで覚えた。読みながらの、意味よりも言葉の響き。」
何が書かれているかばかりに気を取られると、語感や表現の豊かさを見逃すことがある。意自ずから通じなくても、何度も読み返してリズムの良さを楽しみたくなる古典がある。
📖 「読書をなさい」(京極純一)
「勉強のために本を読むことは、ふつう、読書とはいわない。」
「本を読むことは、想像力と感受性の世界のなかで、人間の可能性の広がり、善の能力から悪の能力までの幅の広さを経験することである。人間が自分を捨てて他者を愛すること、また、人間が愛する者と別れてひとり死ぬこと、こうしたことを経験する、これが読書である。」
何かを学んでやろうと思うと、必然ハウツーばかりを読むことになる。ぼくはハウツー本を読むことを読書などとは思わない。著者が言うように、読書は一つの経験的行為である。
📖 読書と友だち(坂本義和)
著者は終戦直後にカントの『純粋理性批判』を読み、「考えることを考える」ことの重要さを思い知ったという。
「国中が思考の短絡におちいっている時に、カントはその逆を私に示したのである。そこには、石造りの壮大なゴシック建築のような、驚くほど強固な思考力があった。」
📖 塩一トンの読書(須賀敦子)
このエッセイのタイトルは著者の姑(イタリア人)の「ひとりの人を理解するまでには、すくなくとも、一トンの塩をいっしょに舐めなければだめなのよ」にちなんでいる。ゆえに、
「本、とくに古典とのつきあいは、人間どうしの関係に似ている。」
〈続く〉