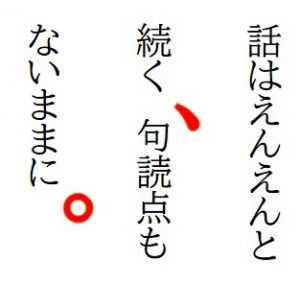3月、4月、5月と会議や打ち合わせや対話がなく喋る機会が激減したので、口はマスクで封印され黙して語らず。今月に入って来客を迎えて3、4人による打ち合わせを3回おこなったが、喋る勘が戻らない。頭は言語を覚えているが、筋肉が発声に戸惑っている。
3月、4月、5月は受注していた仕事が流れたり、延期になったり、テレワークの多い先方の都合で遅延したり。仕事はさほど減っていないが、予定が立たなくなった。仕事が動くのか止まったままなのか、その日の朝にならないとわからない日々が続いた。
6月中旬になって、ようやく動き出した。しかもすべてが同時に。複数の仕事をこなせるのはタイムラグがあるからだ。1週間や半月のズレを利用できるから何とかやりくりできるのである。ところが、今回ばかりは一斉に再起動である。この数年でもっとも慌ただしい日々になっている。数カ月ぶりに再開する仕事をどこまで進めていたのか、うろ覚えである。再開までのリハビリにも時間を要する。
マスクをしていない男性が向こうから歩いてきて、マスクをしているぼくの方を見ているような気がした。ぼくの横を通り過ぎるまでぼくを見ていたように思ったし、軽く会釈したようにも見えた。見たことのない顔なのだが、もしかするとどこかで会っているのかもしれない。
ぼくはその人の顔を知らない。しかし、その人はぼくのマスクをしている顔を知っている。ぼくはその人のマスクをしている顔なら見ているかもしれない。そして、その人はマスクを外すぼくの顔も知っているに違いない。いったいどういうことかと想像していくと、マスクを外さない歯医者とマスクをしたりマスクを外したりする患者との関係がこれに当てはまることに気づいた。記憶があっても認識できないということはよくあることだ。
お互いマスクをしての初対面だと、マスクを外して道で出くわしても認識できずに通り過ぎるだろう。そもそも道で通り過ぎる人々のほとんどの顔は初めて見る顔である。つい先日会ったのに今は知らん顔して通り過ぎる。ぼくたちは顔をどの要素――または要素のどんな組み合わせ――によって個人を認証しているのか。マスクの有無で顔認証は大いに異なるはずである。
と言うわけで、初対面の人とはマスクを外して数秒間顔を真正面で見せ合い、その後マスクを着けて名刺交換することにしている。目は口ほどに物を言うというが、目だけでは顔認証はできそうもない。