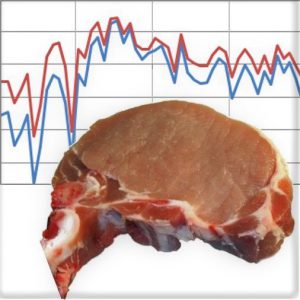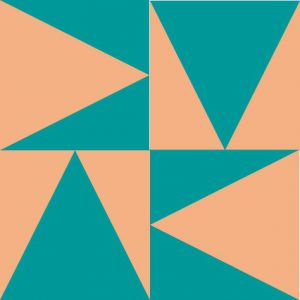リリー・フランキーの『誰も知らない名言集』のあとがきに、あのミスターがイチローに贈った色紙の話が出てくる。色紙にはこう書いてあったらしい。
野性のような鴨になれ
イチロー君へ 長嶋茂雄
可笑しさが半時間ほど持続した。さすがのミスターである。不可解は名言の必要条件ではないが、見る者聞く者をしばし立ち止まらせ、稀に息を詰まらせ、そして余韻を残す。不可解であることは名言の格を上げるのだ。他意もなくつぶやかれることばはおびただしく、ほとんどが消えていくが、稀に名言や迷言として記憶に残る。
名言が吐かれる場面に出くわすことがあるが、周到に用意され練られたものばかりでつまらない。その場で即興的に発せられた名言というものをほとんど知らない。
名言には説明や経緯が欠落しているものが多い。説明を加えたり経緯を推理したりするのは名言を読んだり聞いたりする側である。名言を吐く者には、結実させたことばに至るいろいろな事情や理由があるのだが、そんなことは書かないし言いもしない。だから、おおむね名言は短くて、唐突で、不可解なつぶやきのようなのだ。
つぶやきが忘れられぬ迷言になった瞬間に何度か立ち会ったことがある。
「やっぱりバナナと卵と納豆だな」
唐突にバナナと卵と納豆である。しかも、けろりと「やっぱり」と言ってのけた。ミスターといい勝負ができる。朝食としてはこれで十分そうだが、発作的に朝食に言及したのかどうかはわからない。ここ何十年も物価上昇していない三品目だと気づいたが、つぶやいたのはぼくではないから、真意は不明のままである。気持ち悪いが、迷言を追及してはいけない。
「キャラメルボーイじゃないんだから」
一回り年上の大学の先輩。自分は常連客なのに、ママは一見さんの面倒ばかり見ている。「ママ、ぼくにも水割り売ってよ」と、いいオトナが突然甘え声で拗ねてみせた。「あら、気づかずにごめんね、ぼくちゃん。今すぐに作って売ってあげるから」とママ。先輩、さらに甘えてみせた。「ママ、ぼくはキャラメルボーイじゃないんだから」。二人とも芸達者だった。
「松坂は上手に年取ってるなあ。それにひきかえ、吉永は下手に清純だなあ」
雑談中にため息まじりにこれである。意味はわかった。一理あると思う。松坂は慶子であり、加齢しておとぼけができている。吉永は小百合であり、固着したクリーンなイメージから脱皮できないのは気の毒だ。清純というイメージを背負わねばならない品性は……などと分析しかけたが、そんなことはどうでもよい。きみ、なぜ今それを言わねばならなかったのか?