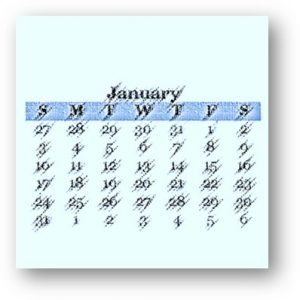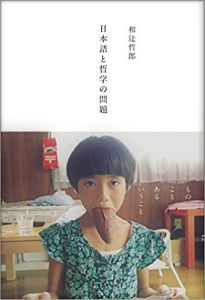オフィスを借りているビルの1階にイタリアワインの専門店がテナントで入っている。お世話になっている(つまり、よく買っている)ので、だいたいの好みを告げて新入荷の中から薦めてもらう。
「ピノネーロでいいのがある?」と尋ねる。ピノネーロはぶどうの品種。フランス語だとピノノワール。
「ちょっと値が張りますが、こちら今日入荷したおすすめです」
「おとなしくて上品なのがいいけれど……」
「ピノの割にはちょっと強いかも。それならあちらの……」と言って誘導された棚には北イタリア産のピノ。イタリア語とドイツ語併記のラベル。オーストリア国境に近い産地だ。
「とてもエレガントです」
エレガントなら上品に見合うはず。と言うわけで、今手元にある。
「おとなしい」「上品な」と形容詞で味と飲み口を伝えたぼくに対し、ソムリエが「強い」「エレガント」という形容詞で返してきた。意味はおそらく共有できているのだろうが、形容詞が味覚の同一性を保証しているはずがない。わかり合えたとしても「だいたい」であり「おおよそ」である。日常の会話ならまったく差し支えない。
数年前に、コロンビアはエルベルダム農園のスペシャリティコーヒーを飲んだ。当時はワインもコーヒーも飲んだ味を文章で表現していた。このコーヒーについてしたためたのが次の文章。
芳醇にして甘い香り。酸味にとげがなくやわらかい。舌に沁みる感触はまろやかで、ほとんど雑味がない。コスタリカの類似クラスよりもやさしい印象だ。
いったい何を表現したのだろうか。そして、いったい何が他人に伝わるのだろうか。形容詞を並べるにしても、形容詞だって無尽蔵にあるわけではないから、同じ表現が何度も繰り返される。誰もが「美しい花」だの「青い空」だのと何度も言い、繰り返してきたはず。花は誰にも同じように美しいわけではなく、空もまた同じように青いはずがないのに、工夫もせずに美しい、青いと言って済ましている。
『コーヒーの科学』(旦部幸博著)に「コーヒーの味ことば」「おいしさを感じることば」などのリストが掲載されている。頻出上位を選んでリストアップしてみた。
香ばしい、コクがある、濃厚な、風味豊かな、まろやかな、深みのある、芳醇な、リッチな、フルーティー、後味すっきり、さっぱり、さわやかな、マイルド、すっきり、ほろ苦い、酸味のある、甘い……
こうしてみると、形容詞は感覚の主観的表現であって、決して感覚を他人に正確に伝えるものではないことがわかる。だから、伝わらないとかわからないという理由で表現者を責めたり追及したりしてはいけない。感想を言うほうも、「おいしい」を筆頭にした、常套的な形容詞を使うのがいい。決して相手が知らないことばを使うべきではない。