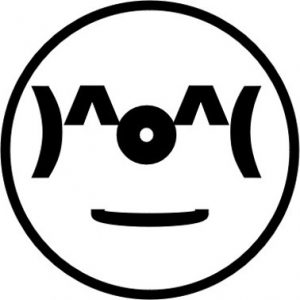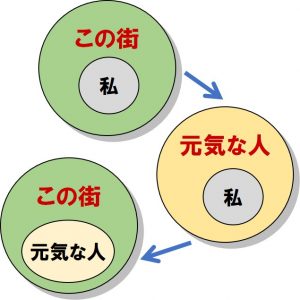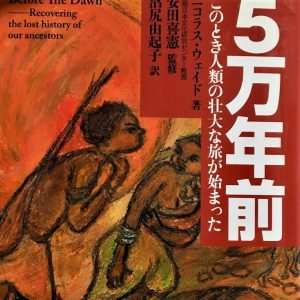ステーキにはステーキソースか塩・胡椒が当たり前だった。この組み合わせが常識・定番で、それ以外の選択肢はないように思えた。ところが、ステーキにわさび醤油が合わされるようになった。シュールで前衛的な印象を受けた。「ん? 合わんだろう」と首を傾げて食べているうちに、この食べ方も定着して、今ではまったく意外性はない。
シュルレアリスムの手法の一つに〈デペイズマン〉というのがある。フランス語で「意外な組み合わせ」を意味する。今、ぼくのデスクの上に書類があり、その上にガラス製のペーパーウェイトが置いてある。「デスクの上の書類とペーパーウェイト」に誰も不意を突かれない。このマッチングは常識も常識、日常茶飯事の光景である。しかし、書類の上にラップに包みもせずに焼きおにぎりを乗せたら、その光景はシュールになる。
対立する二つの要素――または常識的にはなじみそうにない二つの要素――を並べて、コラージュのように貼り合わせてみると、シュルレアリストたちの好む画題が生まれる。かつてロートレアモンが表現した「解剖台の上で偶然に出合ったミシンとこうもり傘」を美しいと思うか思わないかは別にして、意外性にギクッとする。特に解剖台という設定に。
「シュルレアリスムとは、心の純粋な自動現象によって思考の働きを表現しようとすること。理性や美学や道徳から解放された思考の書き取りである」とアンドレが言った。一言一句この通り言ったのではなく、こんな感じのことを言った。アンドレ? フランスの詩人で、シュルレアリスムの草分け的存在、ほかでもないアンドレ・ブルトンその人。
フランス語の“surréalisme”は「超現実主義」と訳された結果、前衛的なニュアンスを持つようになった。ともすれば、現実に相反する概念のように錯覚するが、“sur-“は強調であり誇張だから、シュルレアリスムは現実の表現の一つにほかならない。ある場所において、何かと何かが出合う可能性は無限のはず。頻度の高い組み合わせが当たり前になってきただけの話ではないか。
花札の二月も都々逸も「梅に鶯」だが、ぼくの居住圏では「梅にメジロ」しか見たことがない。子どもの頃から親しんだ花札には定番のマッチングやペアリングがある。たとえば、一月の「松に鶴」は掛軸に多く描かれているし、落語の笑福亭松鶴を思い出す。三月の「桜に幕」は花見光景、また、八月の「芒に月、芒に雁」や十月の「紅葉に鹿」などもいかにも「らしい」。
他方、シュールっぽいのもある。五月の「菖蒲に八つ橋」、九月の「菊に盃」、十一月の「雨に柳と小野道風」、十二月の「桐に鳳凰」等々。すべてにエピソードがあり、知ってしまえば納得できるが、知らずに組み合わせの絵柄だけを見ればかなりシュールである。定番や常識の世界にシュールが現れてドキッとし、何度も見ているうちに慣れてきてシュールが不自然でなくなる。シュルレアリスムが現実や常識とつながっている証拠である。