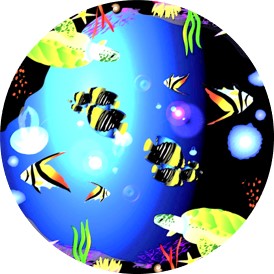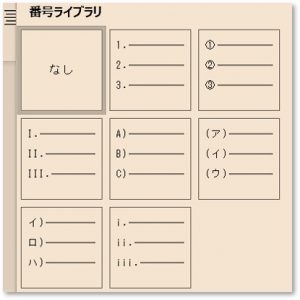醤油を通常の1.5倍量滲み込ませた満月ポンが売られていた。衝動的に買い、買ったことをしばらく忘れていた。赤ワイン摂取中の今夜にそのことを思い出し、袋を開けて赤ワインのつまみにするという暴挙に出た。時代が変わるとまでは言わないが、何かが変わるような予感がした。
o m n i b u s
2020年の1月まで圧倒的な数の中国人観光客が、超過密状態で大阪ミナミの一帯で店に群れ通りに群れていた。今、ミナミから繁盛店すら姿を消しつつある。その最たる現場を今日目撃した。心斎橋の絶対的な商業一等地で長い間インバウンド景気で繁盛していた大手ドラッグストアが閉店していたのである。数年前からすれば「まさか」の――しかし今となっては「さもありなん」の――この事象は、インバウンド景気の終わりの始まり、いや、終わりの終わりを象徴している。
o m n i b u s
巣ごもり需要をねらってメールやDMやポスティングが増えているような気がする。昨日も一通がポストに入っていた。「いつもご愛顧いただいているあなた様に今だけの特別商品のお知らせ」から始まるDM。「今月はボルドーの厳選金賞赤ワイン10本セットが半額以下!」 今だけ? 今月? いや、昨年の春から毎月2回は来ているぞ。
o m n i b u s
長く商いしている老舗の江戸時代のポスターの絵葉書が、その老舗の末裔の家の壁に貼ってあった。萬小間物所は「よろずこまものどころ」だが、その右に書いてある「鼈甲□物類」の□が読めない。何だろうと思案していたちょうどその時、玄関が開いて婆さんが出てきた。「あの、べっこうの次は何と読むのですか?」と聞いてみたが、そんな細かいところまで見たことないと言う。昨日の話だ。
気になるので、帰宅してからついさっきまで、馬の部首を調べ、ネットもまさぐり、辞書も引いているが、まだわからない。ともあれ、諦めのいいぼくが気になって調べているのはちょっとした異変である。
o m n i b u s
最近何かが変わる兆しをよく感じる。あまり他人様と会わないから、人以外のものに感覚が開かれているような気がする。もっとも、何が変わるのかはまったくわからないが……。