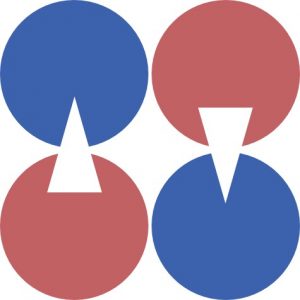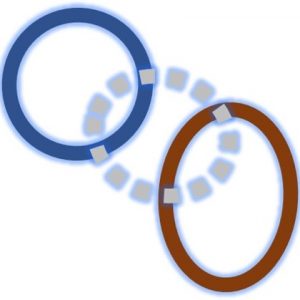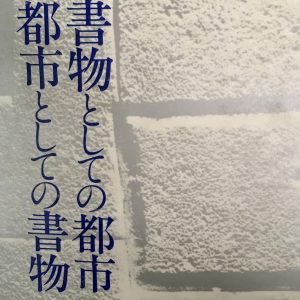一字だけでもいろんな含みが出るのが漢字。では二字ならもっと意味が膨らむだろうと思いきや、実はそうならない。二字、三字、四字……と熟語の字数が増えるにつれて意味は限定されてくるのだ。たとえば「音」の一字は多義だが、二文字の「音楽」になると意味の輪郭がはっきりしてくる。
二字熟語を逆さ読みしてみるとたいてい類義語になる。しかし、同じ漢字を使っていても並びが変わるとまったく別の意味が生成されることがある。それがおもしろいので、二字熟語で遊んでいる。
【色物と物色】
(例)寄席で落語や講談の合間に「色物」ができる芸人を「物色」していたら、異色の芸ができる大学生を紹介してもらった。
白物に対して染めた布地のことを色物と呼んでいた時代がある。寄席で色物と言うと、落語や講談以外の演芸のことを指す。奇術、曲芸、紙切り、物まねなどだ。
物色する対象は、文字通りの色であったり鮮度であったり美しさであったりしたようだが、いろいろある選択肢から一つを選りすぐる様子が伝わってくる。
【回転と転回】
(例)皿をレーン上で「回転」させるという画期的な発想は、寿司業界においてコペルニクス的「転回」となった。
中心に軸があって、その軸をぶれないようにして全体をくるくる回せば回転。そういう意味では、転回という動作も回るのだから同じように見える。しかし、転回にはくるりと向きが変わるイメージがある。向きが180°変わるのがコペルニクス的転回。コペルニクス的回転と言ってしまうと、いつまでもずっと回り続きかねないし、360°回転して止まったら元に戻るだけの話である。わざわざコペルニクスに登場してもらう意味がなくなる。
【下部と部下】
(例)上部組織の「部下」が直属の上司の指示に従わずに、「下部」組織の長の指示を仰いだため、人事が騒ぎになっている。
下部の対義語は上部。下部とか上部は力学的な階層構造を感じさせる用語である。上下には権威象徴的な意味もともなう。他方、部下の対義語は上司である。ここでの上下は職場での人間関係を感じさせる。上部の組織にも部下はいるし、下部の組織にも上司はいる。建物の中では、上部組織のお偉いさんが下の階にいて、下部組織の部下が上の階にいることはよくある。誰がどの階にいても、上意下達という方法は今もよく実践される。
シリーズ〈二字熟語遊び〉は二字の漢字「〇△」を「△〇」としても別の漢字が成立する熟語遊び。大きく意味が変わらない場合もあれば、まったく異なった意味になる場合がある。その類似と差異を例文によってあぶり出して寸評しようという試み。なお、熟語なので固有名詞は除外。