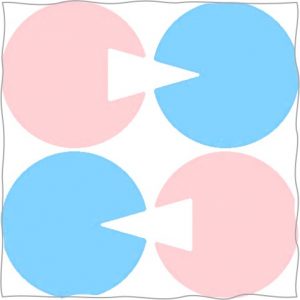会議があまり好きでないので、以前から一人でブレストするのが習わしになっている。自分で文章を書いて自分で推敲することは一人二役の最たるもの。この時期、会議もブレストも相談もすべて自前、一人二役で何とか凌いでいる。
📃 音声POP
店頭から「♪ タターンタタタタン、タターンタタタタン」のメロディが繰り返し聞こえてくる。その場を去った後も耳にこびりついている。そのことをある人にした。メロディとリズムを忠実に再現したら、「ああ、あれは焼き芋の宣伝ですよ」と言った。いやいや、ぼくがいつも耳にするのはドラッグストアのS薬局の店頭で、あそこでは焼き芋など売っていないけどなあ。
ある日、別のドラッグストアKの店頭で流れていた。もしかしてS薬局とKはグループ企業か!? と思った。しかし、同じ日、プチスーパーのM屋からも流れてきた。ぼくの横で中年の女性二人が立ち止まり、「ねぇ、この曲、ドン・キホーテでかかってる」「えっ、ここドンキ?」と会話を交わしたので、ぼく以外に気になる人がいるのを知る。
知人は焼き芋の宣伝楽曲だと言い、ぼくはS薬局グループのテーマソングだと思い、見知らぬ女性らはドン・キホーテのメロディだと指摘した。
宣伝している商品はいろいろであり、曲が流れているシチュエーションはほぼ店頭である。企業や商品特有のものではなさそうだと思い、後日しばらく立ち止まってよく見たら、発生源らしき装置が見えた。繰り返し音声POPを流す、その名も「呼び込み君」。なるほど、それでぼくは何度も呼び込まれたのか。
📃 くずし字
幕と箒、張と強、店と居……極端に字をくずすとよく似てきて、違いがわからなくなる。しかし、心配無用。字はめったにくずされることはない。それどころか、めったに手書きされることもない。
📃 羊
あまり効果がないのはわかっているのに、眠れない時に相変わらず羊を数える人がいる。途中まで数えて、数え間違いしたことに気づき、一から数え直す生真面目派もいるらしい。神経がピリピリして逆に眠れなくなると察する。そこで「羊肉には誘眠効果がある。だから、数えるよりも食べるのが正解だ」と教えてあげるのだが、「ほんとかな?」と疑う。これは遊牧民の常識、催眠術師の非常識なのである。
📃 みんな
「みんなで大家さん」というテレビコマーシャルが最近までよく流れていた。ある街で、もし住民みんなが大家さんになったら、貸主ばかりで借主がいなくなり、兼業の大家さんビジネスは成り立たなくなる。この広告に人を欺く悪意はないと思うが、キャッチフレーズに少々問題がある。「みんな」と言っては誤解を招く。正しくは「内緒で大家さん」である。