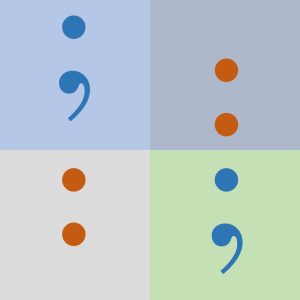某大学のある学生がエイゴの授業中、担当の助教にセミコロンとコロンの違いを尋ねたところ、その助教が「ほぼ同じだよ」と答えた。これが問題視され波紋が広がった。セミコロンとコロンをテーマにしたセミナーが企画された。
セミコロンとコロンが「ほぼ同じ」という発言が問題であるのなら、何が違っているのかを説明する必要がある。説明を申し出る関係者が現れず、また適任者も見つからなかった。残された切り札は一つ、〈文法書世界〉の権威であるセミコロン博士とコロン教授へのお願いだ。ノーを覚悟の上、辛抱強い交渉が続けられた。最終的にはノーがイエスに変わった。そして、セミナーが実現した。公開の場でお二人の肉声が流れたのは初めてのことである。セミナー冒頭の約10分をここに掲載する。
セミコロン(;)博士 セミコロンと申します。小生はカンマ(,)とピリオド(.)の役割を担う者です。しかしながら、カンマよりはやや強く、ピリオドよりはやや弱い立場だと自覚しています。敢えて言えば、機能はピリオドに近いかもしれません。
コロン(:)教授 ピリオドを二つ持つのでよくピリオドと間違われます。しかし、ピリオドの代わりに私を起用する場合は二つの文章が強く関連していることが条件になります。ピリオドのようでピリオドでないのが私の特徴。あ、申し遅れました、私の名はコロンです。
セミコロン(;)博士 小生も二つの文章をつなぎます。文章や比較的長めの句を、接続詞を使わずにつなぐことが多いです。たとえば、「今日はランチに出掛ける予定だ;何を食べるかはっきり決まっているわけではないが」という具合です。
コロン(:)教授 二文に絡む点では私も同じですが、概要を伝える前文を受け、その概要の要素を紹介する文章にリレーします。たとえば、「あのホテルのレストランは3種類のランチを提供している:和食と中華と洋食である」というのが一例です。
セミコロン(;)博士 今コロン教授が話した3つの単語が句になる場合があります。そして、それらの句の中ですでにカンマが使われていたら、句と句を区切る箇所にカンマを入れてしまうと紛らわしくなりますね。その時こそが小生の出番です。また、コロン教授の協力を得ることもあります。一例を示しましょう。「ランチの注文内容は次の通り:営業部、中華弁当5個;研究所、洋食弁当7個;役員、特製松花堂弁当4個」。
コロン(:)教授 セミコロン博士が示された例とやや似た機能が私にもあります。大きな概念を伝えたのちに、具体的な代表例を示すというパターンです。「残業のある日は少なからぬ社員が夜食の手配を希望する:昨夜は8人から申請があった」。
セミコロン(;)博士 文末が括弧で終わる文章が稀にあります。その時に小生がちょっと仕事します。こんな具合です。「彼女はプレゼント用にチョコレートを買った(高額のベルギー製商品);翌日、無事に彼に手渡すことができて幸せだった」。
コロン(:)教授 会話形式で話者のあとに台詞を続ける場合はたいてい私がいます。文献や証言を引用する時にも引用文の前に入ります。
T部長:近くにオープンしたピザ屋のランチがおいしいらしいね。
Y主任:一昨日行きましたよ。リーズナブルですしね。
T部長:一昨日の今日で悪いけど、付き合ってくれよ。おごるから。
Y主任:よろこんで。ピザは大好物ですからね。
【追記】 収録された元の音声はエイゴである。音声から書きおこした文章をニホンゴに訳出した。加えて、お二人の了解を得て、例文の一部をニホンゴ読者が理解しやすいように書き直している。なお、セミナーはこのあと約1時間続いた。「質問には答えない」というのが出席の条件だったので、セミナー終了直後に「ごきげんよう」と言うなり、セミコロン博士とコロン教授は謝礼も受け取らずに会場を後にした。おそらく〈文法書世界〉へ戻られたと思われる。