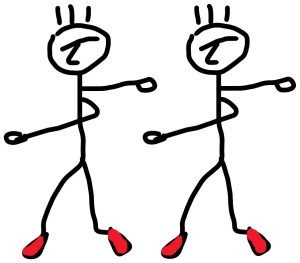親愛なるペーター
長文のメールになりそうな気がするけど、読み流すのは暇な時でいいから。
最近、耳にしたコマーシャルソングがある。『おおブレネリ』のメロディを使った替え歌なんだ。これがきっかけで、♪おおブレネリ……と久しぶりに歌ってみた。一応歌えた。
おおブレネリ、あなたのおうちはどこ
わたしのおうちはスイッツァランドよ
きれいな湖水のほとりなのよ
ヤッホ ホトゥラララ(……)
ヤッホ ホトゥラララ ヤッホホ

正確には「ヤッホ ホトゥラララ」は5回繰り返される。ぼくとしては、「きれいな湖水のほとりなのよ」の次につなぎの一行が欲しいところなのに、いきなり5回も「ヤッホ ホトゥラララ」と繰り返したのはなぜだろう。
ペーター、きみがひいきにしているアンガールズの「はい、ジャンガジャンガジャンガジャンガ……」に似ていないかい? オチがなくて気まずい空気が流れるようなあの感じ。
おおブレネリ、あなたの仕事はなに
わたしの仕事は羊飼いよ
オオカミ出るのでこわいのよ
ヤッホ ホトゥラララ(……)
ヤッホ ホトゥラララ ヤッホホ
2番がこんな歌詞だったとは……記憶とはいい加減なものだね。
ブレネリはてっきり少女だと思っていたけど、仕事が羊飼いならオトナの可能性もある。いや、スイスあたりじゃ、その昔、子どもの時から仕事していたよね。そう言えば、イソップ物語のウソつき少年も羊飼いだった。と言うわけで、ブレネリの年齢は特定できず。
ペーター、きみはスイッツァランド出身のスイス人で、今は東京にいる。もしきみが母国にいて誰かに「家はどこ?」と聞かれたら、「スイッツァランドだよ」と答えるかい? きっとノーだと思う。もっと具体的に町や村の名前を言うものだろう。
でも、東京で同じことを聞かれたら、母国のことだと思って「スイッツァランド」と言うはず。ブレネリも同じ。きっと彼女はどこかの外国にいる。
母国でない某国で住所と仕事を聞かれた。しかも、ブレネリは住所を聞かれたのに国籍を答えた。のっぴきならない入国手続き時の尋問光景か、某国に住んでいるブレネリが不審に思われて職務質問を受けている様子ではないか。
歌詞にするとやわらかい調子になったが、ほんとうは次のような緊張感のある場面だったのかもしれない。
「住所は?」「スイッツァランドです」「スイッツァランドのどこだ?」「湖水地方です」「仕事は?」「羊飼いです」「家業の手伝いか?」「ええ。狼が出るので怖かったです」「そんなことは聞いておらん」
もしこんなやりとりだったら、重苦しく気まずい空気になったはず。「ヤッホ ホトゥラララ」でとぼけるのもやむをえないな。
なんでこんなことをきみに書いているのかと言うと、スイス民謡として親しまれているこの歌の背景に何か裏があると睨んだのさ。で、きみの意見を聞きたくなったというわけ。
数日後、ペーターから返信があった。
ぼくはね、日本に来る前はこの民謡のことは知らなかった。ブレネリにも違和感があった。だって、ブレネリというのはたぶん英語で、スイスではフレネリと発音するんだ。日本に来てからこの歌を知り、何度か歌ったことがあるし、ドイツ語の原作詞も調べたことがあるよ。
きみのメールの解釈は、たぶん考え過ぎだな。異国で新しく友達になった誰かが素朴に質問しただけだと思うよ。
そりゃそうだ。ペーターの言う通りかもしれない。長ったらしい駄文を読ませてしまった。翌日、お詫びのメールをすることにした。
メールを打ち始めたちょうどその時、ペーターからのメールが受信ボックスに入った。
昨日メールを送った後に、きみの解釈が考え過ぎだと書いたのはどうかと思い、念のためにいろいろと調べてみたよ。驚いたね。あの歌詞には続きがあったんだ。
おおブレネリ、わたしの腕をごらん
明るいスイスを作るため
オオカミ必ず追い払う(……)
おおブレネリ、ごらんよスイッツァランドを
自由を求めて立ち上がる(……)
「きれいな湖水のほとりで暮らし、小高い丘で羊飼いをしていたわたしたちに、ある日突然オオカミが襲ってきた。追い払え、負けてなるものか、自由と幸福と平和を守るのだ……」という時代背景から生まれた歌だとペーターは続けた。
そして、「これはヨーロッパの穀倉地帯で今起こっていることの予言かもしれないな」とメールを結んでいる。
ペーターにショートメールを送った。「ヤッホ ホトゥラララ」
すぐにペーターから返信があった。「ヤッホホ」