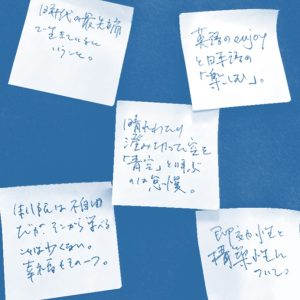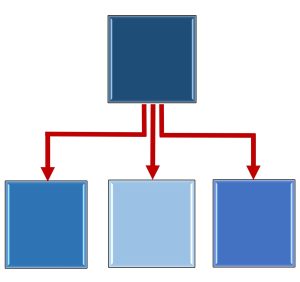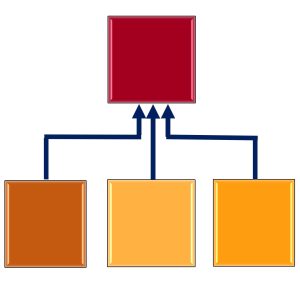メモや文章はひとまずノートに手書きしている。システム手帳なので分厚くなりかさばる。ランチやちょっとした雑用で出掛ける時は携えない。しかし、そんな時にかぎってよく気づくし記録したくなる話題に出合う。最近は付箋紙と水性ボールペンだけポケットに入れて出る。付箋紙には見出しか要点だけを記し、長い文章は書かない。
そうしたメモは数日以内に手書きで文章にしておく。かなり日が経ってしまうと、メモをした意図すらわからなくなる。読書量もノートに書くメモの数も減る猛暑の季節。付箋紙由来のメモから雑文を起こしてみた。
📝 いま生きている者はみな時代の最先端にいる。断崖に立って見えない未来に直面しているようなものだ。最先端で生きるなんてカッコいいようだが、不安で落ち着かないし、決して楽観的にはなれない。人類はいつの時代も宇宙の危なっかしい場所に居続けてきて、何とかリレーしてきて今に至っている。
📝 英語の“enjoy”には目的語がいる。日本語の「楽しむ」はそれだけで使える。何を楽しむか言わないのは明快ではない。しかし、文脈や行間からわかることが多いから、「何々を楽しむ」といちいち几帳面に言うのは少々野暮である。
📝 午前10時。全方向をくまなく見渡して空を仰ぐ。薄雲は一条の線も引かず、白雲は小さな欠片も固めず。つまりは、晴れわたり澄み切った青天白日。この光景をいつもいつも「青空」と片付けてしまうのは怠慢ではないか。
📝 マスクという制限、ステイホーム(外出自粛)という制限、少人数の黙食という制限。制限は不自由だ。制限が課されると、制限がなかった過去を思い出す。「自由はいいなあ」とつぶやく。この過去の思い出があるからこそ、制限解除後の未来の自由が想像できる。自由と自由がサンドイッチのように制限を挟んでいる状態をイメージしている。
📝 半年ぶりの他県でのリアル研修だった。テーマは企画。企画について新しい発見があった。即効性と構築性(またはアドリブと計算)、感覚と戦略、瞬発と熟成などの二項概念がもたれ合って一つの形を作っていく。それが企画という仕事である。