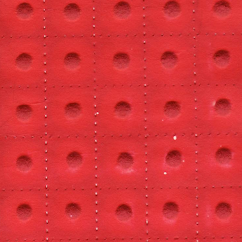最近、バーチャル世界だけでなく、リアル世界でも〈ごっこ遊び〉が目立ち、しかも大仕掛けになっている。五輪もIRもある種のごっこ遊びだ。また、小さなごっこのつもりで始めた個人が、知らず知らずのうちに巨大な電子システムの中に巻き込まれていたりする。リアルかバーチャルなのか、よくわからない。
本来ごっこはリアルを真似たたわいもないバーチャルな遊びだった。ごっこには複数のプレイヤーが参加し、少なくとも二人を必要とする。稀に一人でごっこ遊びする子がいるが、その場合でも仮想の誰かをイメージするので、実際は二人で遊んでいることになる。
誰かに成り切ってロールプレイするのがごっこ。ヒーローと悪人、医者と患者、売り手と買い手などと役割が分担される。それは人間関係ゲームでもある。カイヨワの言を借りれば〈ミミクリー〉の範疇に入る。いわゆる模倣や真似事。ごっこは本物を模倣するフィクションで、しかも現在進行形の脚本と即興的な演出を特徴とする。
🔫
小学生だった昭和30年代、テレビのある家は町内に一軒か二軒しかなかった。引きこもっても特に遊べる材料が家にない。必然、子どもは屋外に出る。当時、近所に団地が建ち、敷地には給水塔があった。視界を遮る構造物のお陰で〈戦争ごっこ〉のゲーム性が高まった。三角ベースボールに飽きた頃だ。小遣いで買ったブリキ製の銃と火薬を持って出掛ける。銃は一発撃つごとに火薬を充填するタイプのものだ。
火薬と言っても、危険なものではない。紙に火薬を盛りつけた花火の一種。火を使わない分、花火より安全である。これを銃に充填して引き金を引く。撃鉄が火薬の上に落ちてパーンという乾いた破裂音がする。音だけで玉は飛び出さない。
破裂音がするだけのこんな銃でどんなふうに遊んでいたのか。集まった子どもたちが敵と味方に分かれる。建物や給水塔や植え込みに隠れて、敵を見つけたら飛び出してパーンと撃つ。どっちが先に撃てるかが勝負。玉が当たるわけではないから、銃口が正確に相手に向けられて「バーチャル命中」したかどうかは阿吽の呼吸で決める。当てられたと思ったら「あ~」と叫んで倒れる。当たったか当たってないかでもめることもあったが、子どもなりに取り決めたルールに従っていた。
みんながこういう遊びをしているのを知って仲間に入った。銃は父が買ってきてくれたのだが、その銃、みんなが使っている平玉火薬用ではなく、巻玉火薬用のものだった。つまり、ぼくだけがそのつど充填せずに連射するというアドバンテージを得たのだ。「ずるい」と皮肉られたが、敵味方に分かれる時にぼくを仲間にできれば作戦は半ば成功だった。連射の優位性を十分に生かしたわけだが、一発ずつ充填してこその遊びだったと思う。敵が火薬を入れ替えるタイミングを見計らって撃つことに妙味があったのだから。