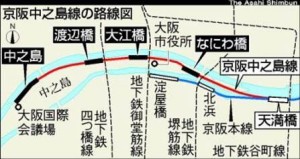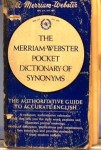「三人寄れば」とくれば「文殊の知恵」。なぜ「三」であって「二」ではないのか。三のほうが和するというのは根拠不十分だし、二は対立や背反を感じさせてネガティブであるというのも深読みすぎる。生半可に考察するわけにはいかない。「女三人寄れば姦しい」というのもあるから、三が二よりも優位であるとも言い切れない。二よりも三が座りが良い感じがしないでもないが、これも偏見かもしれない。
「三人寄れば文殊の知恵」に相当する英語は、“Two heads are better than one.”である。直訳すると「二つの頭は一つよりもすぐれている」。三人ではなくて二つの頭、つまり、二人の頭脳なのである。英英辞典をひも解くと、“Two people working together can solve a problem quicker and better than a person working alone.”と説明されている。「一人でするよりも二人一緒にするほうがより速く上手に問題が解決できる」と言っている。
「一人より二人のほうがいい」と明言する英語に対して、「三人が二人や一人よりも優れている」などと言わずに、ポツンと(あるいはさらりと)三人を持ち出し、それが文殊の知恵になるんだよと言うのは日本的なのだろうか。ちょっと気になるので、他言語ではどういう表現をしているのか調べてみた。
“Deux avis valent mieux qu’un.” フランス語では「二人の意見は一人の意見よりも価値が高い」と言う。英語で頭だったのが意見に変わるが、「2>1」である。“Due teste valgono più di una.” イタリア語は英語と同じで、「二つの頭」であり、これも「2>1」。ドイツ語はどうか。“Vier Angen sehen mehr als zwei.” 英仏伊と違い、「四つの目が二つの目よりもよく見える」である。意見や思考が眼力に変わる。しかし、お化けでないかぎり、四つの目とは二人のことだから、これもまた「2>1」だ。
ここで、欧米では「2>1」というのが一般的と書こうと思ったが、念のためにスペイン語をチェックしてみた。“De un consejo de tres emana la sabiduria.” 調べてよかった。「三人の助言から知恵が生まれる」。「三が二や一よりも優れている」とも言っていない。これは「三人寄れば文殊の知恵」に酷似している。他にも例外があるに違いない。しかし、少なくとも英仏伊独の「二」と日本の「三」は対照的である。東洋思想では「三」が縁起のいい数字であると何かに書いてあった記憶があるが、確証はない。
さて、「三人寄れば文殊の知恵」の三人がどんな人間を想定しているのかが気になる。「全体は部分の総和に勝る」(アリストテレス)に従えば、全体が文殊の知恵であるから、部分は文殊の知恵以下ということになる。おそらくこの三人はどこにでもいる凡人なのに違いない。凡人でも頭を寄せ合って意見を言い合い相談してみたら、文殊菩薩レベルのアイデアが出るということなのだろう。但し、誰もが経験する通り、その確率は高くない。これは一種の励ましと見るのが正しい。一人でできることが三人寄ってたかっておじゃんになることも稀ではないのだから。