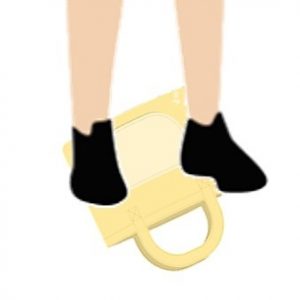みるみるうちに、さっきまで命ある樹々の枝葉だったのが次から次へと地面に落ち、ゴミと化していく……時々出くわす街角の光景だ。公園事務所の職員(または下請け業者)はてきぱき剪定し、ばっさばっさと伐採し、時にはぐいっと抜根する。迷いも未練もすっぱり断ち切る。当然だ。いちいち感情移入していたら仕事にならない。
室内で植物を育て観葉しているぼくのような者にとっては、剪定は恐る恐る身構えるような作業になる。先月もらったサクラの枝の切り花がピークを過ぎ、そろそろお別れする時になった。緑色が残っていて新しい芽がついている小枝を数本、15センチほどの長さに切って、切り口に発根促進剤を塗って水に漬けた。半月経っても根が出る気配はなく、枝も変色し始めた。うまくいかなかった。
元気がない別の植物も同じように処理して水耕している。ダメもと覚悟の上だが、うまく命をつなげればと思う。こんなことをここ数年続けているうちに、まずますの確率でうまく発根することを知った。土に植え替えて面倒を見れば上々に育つものがある。こうして、蘇生やリレーのための挿し木が剪定時の習わしになった。
観葉植物は春先から夏の暖かい時期に剪定する。切った枝葉のうち良さそうなものを選んで、水に浸したり土に差し込んで発根を期待する。一般的に、観葉植物を挿し木する時、最初は水耕で育てるほうが根が出やすい。ところで、なぜこんな作業をしているのかと言えば、元の植物と同じものを増やすためである。
放置しておくと、鉢植えの観葉植物は根詰まりするし栄養状態も悪くなる。だから毎年剪定し、数年に一度は新しい土に植え替えてやる必要がある。剪定した枝葉をうまく人工的に培養すれば、クローンのように増殖してくれる。しかし、増やして誰かに譲るわけではない。鉢の数が増えると世話する手間も増える。週一回の水やりに半時間もかかる。にもかかわらず、なぜそこまでして増やすのか。
剪定した茎や枝をゴミ箱に捨てる際に芽生える罪の意識だ。せめて一本か二本を挿し木にすることで償っている。間違いなく最初の頃はそうだった。しかし今では、罪の意識や償いではなく、発根達成感を求めているような気がする。モンステラなどはこんなふうに挿し木していって、子孫兄弟の鉢を五つも六つも増やした。今年も剪定と挿し木の季節がやってきた。ゴールデンウィークの頃から忙しくなる。