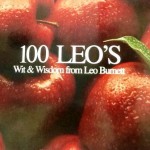〈書評輪講カフェ〉と命名した読書会を不定期に主宰している。会合開催の前週や当該週になると操られたように読書について一考する。もう何年もこんな状態が続いている。
ところで、最近あまり本を読んでいない。今年に入って50冊ほど買っているはずだが、本気で読んだのは片手にも満たない。大半の本の取り扱いは、ページを適当に繰って拾い読みするか、目次をざっと走査して狙いすました章だけを読む程度である。冬から春にかけてのこの時期だからというわけではない。読書離れは突然予告なしに起こり、そしてしばらく続く。やがて、ダイエットの後にリバウンドが待ち構えているように、再び読書にのめり込む周期に入る。
「本を読むというのは、私たちの代わりに他の誰かが考えてくれるということだ。一日中おびただしい分量を猛スピードで読んでいる人は、自分で考える力がだんだんに失われてしまう。」
こう言ったのはショーペンハウエルだ。自分以外の誰かがすでに考えたことを無思考的になぞるのが読書行為であるとはやや極論かもしれない。だが、そうではないとも言い切れぬ。本の内容を素材にして考えるほうが、本を手にしないで考えるよりも負担は少ない。もっとも、本を読んでも思考力が衰えるのなら、本を読まないとバカはさらに加速するだろう。ショーペンハウエルの言は、「考える力のある人は読書に依存しない」と読み替えてみるのが妥当である。そう解釈しても、では、考える力の乏しい人がどのように読書に付き合えばいいのかという答えは出てこない。
何にでも関心を示して精進するわけにはいかない。教養はあるほうがいいし、ものは知らないよりも知っているほうがいいだろう。しかし、どれだけ頑張っても、知っていることは知らないことに比べたらつねに一握りにすぎない。「えっ、読書家なのに、あの小説はお読みになっていない? 絶対読まないといけませんよ」と年下の知人に忠告されたと仮定しよう。「先生ともあろう人が……」と追い討ちもかけられ、これは聞き捨てならぬと、ぼくのお説教が始まる。
「あいにくぼくはその作家に関心がない。ペンネームの漢字の読み方すら間違って覚えていたくらいだ。ベストセラーか評判の作品かどうか知らないが、なぜ右にならえのように読まねばならないのか。一億総同本読みか。では、聞くけどね、きみはガルシア・マルケスの『百年の孤独』を読んだかい? ほら、読んでいない。ノーベル賞作家だ。村上春樹がまだ受賞していないあの賞。『百年の孤独』でも他の本でもいいが、ぼくはきみに一度でも絶対読まないといけないと言ったことがあるかね? 断じてない! 本というのは人それぞれ何を読んだっていいんだ。いや、何も読まなくってもいい。世の中に読まねばならぬ本はなく、他人から勧められて半ば強制されるように読むべき本もない。ただ読んでみたい本があるのみ。きみとぼくの読む本の大半が重なるなんて、こんなおもしろくない話はない。重ならないからこそ、ぼくはきみの読んだ本の印象を聞いてみたいと思うのじゃないか……」
説教は、おそらく収まらない。さて、福沢諭吉の『学問のすゝめ』に読書に言及する一編がある。学問ということばを小難しく考えることはない。初歩的な意味は「学び習うこと」にほかならない。つまり、学習。一般的には教師や書物から新しい知識を授かることである。このことを承知した上で、同書の十二編を読んでみる。
学問はただ読書の一科に非ずとのことは、既に人の知るところなれば今これを論弁するに及ばず。学問の要は活用に在るのみ。活用なき学問は無学に等し。(……)学問の本趣意は読書のみに非ずして精神の働きに在り(……)
読書は学問の出発点でもなければ本質でもないということだ。読書によって何かを学んで習っても、インプットだけでは無学と変わらない。学習で重要なのは、活用だ、精神の働きだと言うのである。ショーペンハウエルが指摘したのもたぶんこれだ。本を読むな! と言ったのではなく、書かれていることを覚えるだけでは考えないだろう、生かさないだろう、精神が面目躍如として生き生きとしないだろう……というようなメッセージとして読み取れるのではないか。
読んだら書けばいい。自分の思考の拠り所を基礎として書評をしたためればいい。したためた書評を誰かとシェアすればいい。書評を読み返し思考と精神を時折り更新すればなおいい。このような繰り返しが日々の生き方・仕事の仕方に反映されてくる。机上の読書が現実に降りてくるのである。