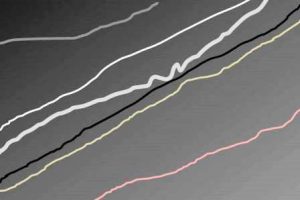賑わっているカフェ。カウンターで注文の際に「店内は大変混み合っておりますので、先にお席の確保をお願いします」と言われることがある。促されるまま、注文を後回しにして席を探す。予約札があるわけではないから、自分の席のしるしになるものを置くしかない。たいていはハンカチ。ハンカチがなければノート。「命と同じくらい大切なノート」と広く宣言しているにしては、不用意に置くものである。
カフェ賑わい空席わずか 片隅のテーブルのノートは自分のしるし / 岡野勝志
確保したテーブルに注文したコーヒーを自分で運ぶ。隣りの男性はテーブルに所狭しと書類や本を広げ、パソコンに向かっている。彼はトイレに立つ。すべて置きっ放し。おまけに、上着も椅子にかけたまま。なかなか戻ってこない。こっちがドキドキしてしまう。彼の陣取った場所はしるしだらけ。しかし、それは席外しの証でもある。この国の人々の安全安心ボケ、ここに極まる。
街歩きの途中で一休みする。公園のベンチに腰掛けるのもいいが、喫茶店を探してコーヒーにありつくのが愉しみの一つ。チェーン店が一杯200円か250円でまずまずのコーヒーを提供する時代だ、年季の入ったマスターが仕切っている喫茶店の倍額のコーヒーが引けを取るはずがない。しかし、稀にハズレがある。昨日がそうだった。ハズレの後に帰宅して真っ先にすること。お祓いではない。自分でエスプレッソを淹れて飲み直し。
初めて入る店の気配は店名と店構えから判断するしかない。まあいいのではないかと直感して入った。昭和レトロだが、インテリアも照明も悪くない。とびきりうまいのを淹れてくれそうな雰囲気のマスター。待つこと5、6分。コーヒーを一口すすった瞬間、レトロな喫茶店は「場末の茶店」へと転落した。
ああ、レトロな構えにほだされた
注文したのはブレンドなのに
出てきた一杯はアメリカン
香りのない超薄味のアメリカン
砂糖入れなきゃ飲めやしない
自分の勘の悪さが情けない
『涙――Made in tears』を思い出す
♪ メッキだらけのケバい茶店……と
中島みゆき調で口ずさんでみるか
コーヒー運は悪くないのに……
威張っているような砂糖壺を睨み
420円を放り出すように置いてきた