学生の頃からの個人的な理由があって、ぼくの旅先はほぼヨーロッパ、とりわけイタリアとフランスに集中している。たわいもない理由なのでここで公にするほどでもない。何かの機会があればいつか書いてみるかもしれない。ともあれ、他の国へも少々旅はしている。イタリア語と英語はまずまずなので、語学が苦手な人に比べれば危機回避の術は少しは長けているはず。それでも、独学で少し齧ったフランス語、ドイツ語、スペイン語のほうは、絶対的なリスニング量が少ないから、たかが知れている。出掛ける直前または現地に行ってから、使う可能性の高そうな表現のみを集中的に覚えて凌いでいるのが実情だ。
旅行会話集の類は場面を幅広く網羅しているから、何もかも覚えようとしても無理である。挨拶と道や場所の尋ね方、それに料理の注文方法の3章だけを押さえておけばいい。買物好きにとっては数字の聴き取りはかなり難しいが、必須だろう。また、会う人のほとんどが初対面なので、「お元気ですか?」に出番はほとんどない。
ところで、語学はまったくダメという人でも、絶対に覚えておくべき必須表現が一つある。それは、「すみません、トイレはどこですか?」である。街中であろうとカフェやレストラン内であろうと、この言い回しの頻出機会はとてつもなく多い。
欧州の旅ではトイレ探しにかなりの時間とエネルギーを費やすことになる。ぼくは決して頻尿ではないが、あちらの連中に比べると日本人はトイレが近いような気がする。外出すると喉がよく渇くのは、湿度が低くて空気が乾燥しているせいかもしれない。ミネラルウォーターが安いから部屋にいてもよく飲むし、食事の折にも当たり前のようにワインと水を飲む。水分摂取は間違いなく増える。加えて、公衆便所が極端に少ない。モールやデパートでさっさと用を済ませるわけにもいかない。広い駅でもトイレの場所は一ヵ所にしかなかったりする。しかも、そのトイレの場所を探すのが一苦労なのである。探し当てたと思ったら、そこが有料トイレ。そう、だから「トイレはどこ?」とセットにして小銭をいつも携えておかねばならない。紙幣をくずすために売店で水を買って飲むと余計にトイレが近くなってしまう。
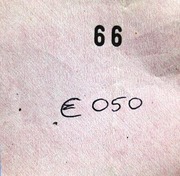 この写真は50ユーロセントと手書きされた有料トイレの領収書である。スタンプで番号を押してあるが、単なる事務処理用であって、その番号のついた便器へ行けという意味ではない。入口で当番しているおじさんかおばさんにお金を先払いし、レシートを受け取って改札を通過する。駅に改札がないくせに、トイレにはちゃんと設けてある。こんな領収書をもらっても申告できるわけでもあるまいが、いつもの癖で財布に入れてしまう。半月も旅したら5、6枚はたまる。なお、男性よりも女性のトイレ代のほうが料金が高い場合もある。
この写真は50ユーロセントと手書きされた有料トイレの領収書である。スタンプで番号を押してあるが、単なる事務処理用であって、その番号のついた便器へ行けという意味ではない。入口で当番しているおじさんかおばさんにお金を先払いし、レシートを受け取って改札を通過する。駅に改札がないくせに、トイレにはちゃんと設けてある。こんな領収書をもらっても申告できるわけでもあるまいが、いつもの癖で財布に入れてしまう。半月も旅したら5、6枚はたまる。なお、男性よりも女性のトイレ代のほうが料金が高い場合もある。
急に尿意をもよおした。長時間探しているうちに漏らしそうになる……大いにありうる話である。こうなると、フランスならカフェに、イタリアならバールに行ってコーヒーを注文するしかない。現地の人は店のどこにトイレがあるか知っているから、店に入っても飲み物を注文せずにさっさと用を済まして出て行く。旅の異邦人はそういうわけにもいかない。我慢の限界であっても、エスプレッソを頼んでぐいっと一杯飲み干し、バリスタに「トイレはどこかな?」と聞く手順を踏まねばならない。
「そこ」とか一語で指を差されて「そこ」を目指しても、推測した「そこ」にトイレが見つからないことはよくある。隠れ家みたいになっていたりする。「突き当りの左に階段がある。そこを降りて正面だよ」などと説明されるのはありがたいが、語学オンチにはこれがまた大きな負荷になるだろう。やっと無事にトイレに入ったら、今度は鍵のかけ方がわからない、水を流すボタンの位置がわからないなどは当たり前。おまけに、怪しい先客がいないかの用心も欠かせない。天井から釣り下がっている紐などを下手に引っ張るとブザーが鳴るから要注意だ。
イタリア語圏のスイスの街に行った時の話。言葉は困らなかったが、トイレで困った。外出中はめったにないことなのだが、その時は便意をもよおした。トイレの場所を聞いて駆け込んだ。係はいないが、ドアのノブの下に硬貨を入れて中に入る有料トイレだった。数字が書いてあるので、ユーロ硬貨を入れるが返却口に戻るばかりで、ドアは開いてくれない。ノックをしたが中はどうやら空いている。血迷った眼でよく見たら、ユーロではなくフランだった。そうか、イタリア語圏だけれど通貨はスイスフランなんだ……。
限界を感じながらも息せき切って両替カウンターへ走り込み、50ユーロ紙幣を差し出してフラン紙幣に替えた。その紙幣を握りしめて売店へ行き、キャンディか何かを買って小銭でお釣りを受け取った。再びトイレに戻り、震えの来ている指先をもどかしくも制御して硬貨をつまみ、投入口に狙いを定めて放り込んだ。ドアが開いた。まるで「開けごま」と祈る思いであった。スイスフランなど手元にあっても仕方がないから、乗り物と飲食に使いきった。手元に残ったのがこのコインである。帰国後しばらくは、このコインを見るたびに条件反射的に便意を催したものだ。
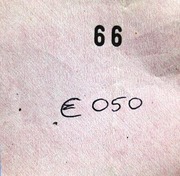 この写真は50ユーロセントと手書きされた有料トイレの領収書である。スタンプで番号を押してあるが、単なる事務処理用であって、その番号のついた便器へ行けという意味ではない。入口で当番しているおじさんかおばさんにお金を先払いし、レシートを受け取って改札を通過する。駅に改札がないくせに、トイレにはちゃんと設けてある。こんな領収書をもらっても申告できるわけでもあるまいが、いつもの癖で財布に入れてしまう。半月も旅したら5、6枚はたまる。なお、男性よりも女性のトイレ代のほうが料金が高い場合もある。
この写真は50ユーロセントと手書きされた有料トイレの領収書である。スタンプで番号を押してあるが、単なる事務処理用であって、その番号のついた便器へ行けという意味ではない。入口で当番しているおじさんかおばさんにお金を先払いし、レシートを受け取って改札を通過する。駅に改札がないくせに、トイレにはちゃんと設けてある。こんな領収書をもらっても申告できるわけでもあるまいが、いつもの癖で財布に入れてしまう。半月も旅したら5、6枚はたまる。なお、男性よりも女性のトイレ代のほうが料金が高い場合もある。