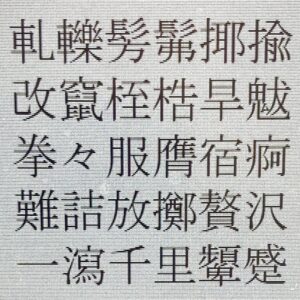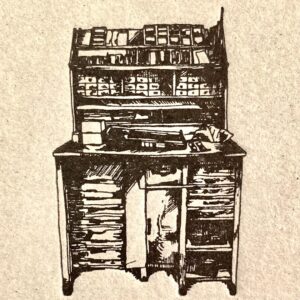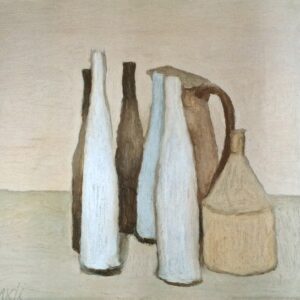「手ぐすね引く」という慣用句はよく知られている。「十分な用意をして機会が来るのを待ち受ける」という意味も何となくわかるし、時々使うこともある。そのくせに、手ぐすねの「くすね」のことはよく知らない。
弓の使い手が手ぐすね引く様子など実際に見ることはめったにない。そこでAIの“Google Gemini”に指示してモノクロのイラストを描いてもらうことにした。何度も指示を変えて出来上がったのが下図である。

弓と矢じりの少し下が交叉するところを左手で摑み、右手でおそらく「くすね」を弦に塗っているらしい。「らしい」とは変だが、そういうシーンを描いてほしいと指示したから、おそらくそうなのだろう。
くすねとは漢字で「薬煉」と書く。松脂を油で煮て煉った粘着剤だ。これを手に取って弓の弦に塗って弦を補強するのである。このことを「手ぐすね引く」と言い、十分な準備をして待つという意味になる。
AIのお陰で、時は戦国時代の差し迫る合戦を控えた場面、用意周到な態勢で敵を待ち構える鎧武者を浮かべることができる。「手ぐすね」というものがあるのではなかった。また、「手ぐすね引く」の引くは弓を引く動作のことではなかった。「手でくすねを塗る」ことだった。引くとは塗るの意なのである。
こういう背景を知ってしまうと、「手ぐすね引く」という慣用句を使おうとしても慎重にならざるをえない。実感がないし、別の代替表現でも何とかなるからだ。たとえば「包丁をよく研いで食材を待つ。これなら体験があって実感が湧く。実感とことばがつながっている。