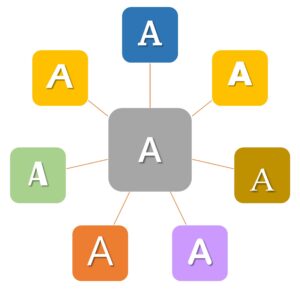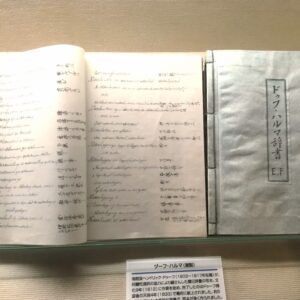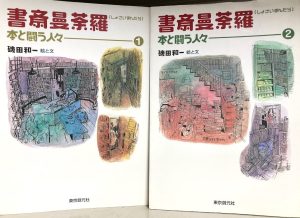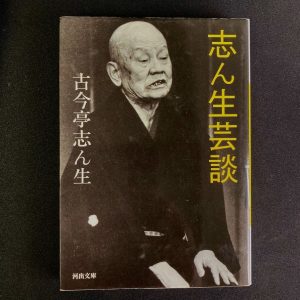🔃 「いつまで仕事を続けるのか?」と他人に聞かれたことはない。カフェで自問したことはある。「仕事を続けているかぎり、平日ではない〈週末〉を毎週迎えることができる」と自答した。
🔃 複数の仕事の一つ、講師業から昨年手を引いた。これで小難しいことを考えなくてもよくなるとほっとしたが、闇の中で藻屑と化した知識や知恵が一点の小さな光明に出合っったかのようによみがえる時がある。
🔃 力を失って低迷するA(というモノ、人、場……)に替わって、期待を背負ったBが現れる。うまくいけばいいが、仮にBも低迷するようなことになれば、もうすでにないAに戻ることはできない。AもBも失ったらどうなるのか……決して不安に陥ることはない。どうにかなるから。
🔃 様々な関係の中を生きていくためには〈順接〉だけでは不十分で、順接と同じ数の〈逆接〉も用いなければならない。
🔃 漢字の標識よりもアルファベットの標識のほうが洒落て見えるのは、たぶんに偏見である。表意文字を見慣れているから、表音文字が新鮮に見えているだけだ。精通していない外国語の地名など、地名の文字が意味を伝えていない時、標識そのものがビジュアル的な存在になり、アート性の強いデザインと化する。示される矢印の方向がかなりアバウトなのも悪くない。
🔃 『はずれ者が進化をつくる』という本を再読した後に街角に佇めば、個性に溢れ、答えがなく、ありのままに理解することはできず、普通や平均のない街の形相が見えてきた。読書して知り過ぎることはないが、少し本を読んでおくほうがいろいろと見えてくる。もちろん、街角も本と遜色のないヒントを授けてくれる。
🔃 場の記憶、人の記憶、過去の記憶……記憶のおかげで世界が広く見えてくる。記憶のおかげで、過去と現在と未来がつながっていることを実感する。