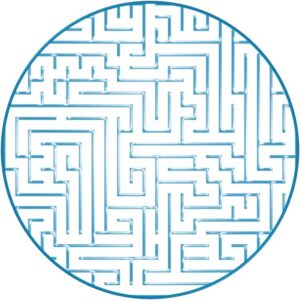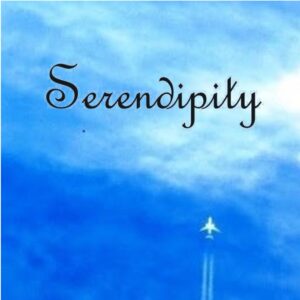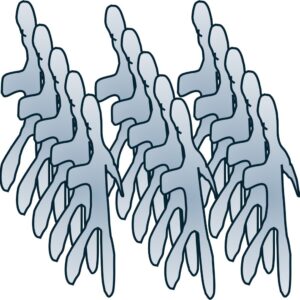ここ数年、某企業から依頼されて「人生100年時代」のコラムを書いてきた。人生100年のどの断面を切って文を綴るか。指示はなく、主題はすべて任された。
森へ分け入れば樹齢100年などは珍しくない。人生100年時代もいよいよ現実味を帯びてきたと言われるが、親族や周辺を見渡しても90年代がやっとこさで、人生100年に現実味はなかった。しかし、3週間前に伯母(父の姉)が亡くなり、享年102と聞いて人生100年時代が一気に身近になった。
桜には散る理由がある。来年も咲くためだ。しかし、人が長生きして死することに、桜ほどの明快な理由が見当たらない。
高齢者が「私めは後期高齢者の仲間入りしました」とギャグっぽく言うことはあっても、自らを生真面目に「高齢者」と呼ぶことは稀だ。そう名乗る時は優遇されるか何か特典が受けられる時に限る。同じく、「シニア割引クーポンをお持ちですか?」と聞かれて頷くことはあっても、自らを「シニア」と言うこともない。
シニアとは年長者のことである。しかし、シニアハイスクールのシニアはジュニアに対しての表現。シニアにしても以前のシルバーにしても年上やお年寄りのことだ。人の呼び方には「長幼」が基軸になるのがこの国の習わし。
英語の授業で兄を“older brother”、弟を“younger brother”と教えられたが、欧米では年長や年少をあまり意識しない。つまり、誰かに兄弟を紹介する時は“He’s my brother”とだけ言う。日本人は老いも若きもが老若を意識する。
さて、人生100年時代の若くないコラムニストのぼくは、いろいろ考えた挙句、コラムでは高齢者を「シニア」と書いてきた。しかし、シニアを多用するのは芸がないので、シニア自らが生き方・暮らし方を語ることばをなるべく引用するようにした。そうすると「私は」とか「ぼくは」と語る主体性のあるシニアを描き出せたのである。
「生命のある間は幸福がある」(トルストイ)
「幸福な人間とは、自分の人生の終りを始めにつなぐことのできる人のことである」(ゲーテ)
トルストイのことばもゲーテのことばも死を暗示している。そう、人生100年時代と言いながら、死についてまったく言及しないほうがむしろ不自然なのだ。人生100年時代とは人の生の有限を物語る。そう感じながら、最後のコラムを書いたのを覚えている。