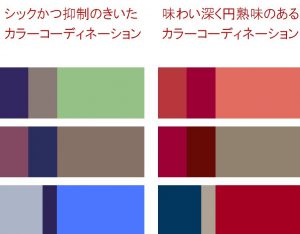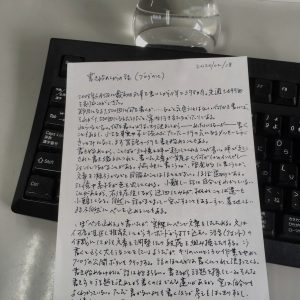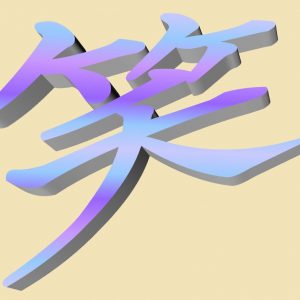ある日のこと。
雨が降っていた。出掛けねばならない。傘がいる。井上陽水には傘がなかったが、幸い傘はあった。右手に傘、左手に鞄という出で立ち。両手がふさがる。
前を知り合いの後期高齢者の女性が歩いている。右手に傘、左手に少し大きめのキャスター付きバッグ。濡れた車道で足を滑らせそうで、冷や冷やする。追いついて話しかける。「どちらまで?」「センターです」。センターが何か知らないが、関心はそこにはない。「両手がふさがっているので、転ばないようにお気をつけて」とお節介した。人は、転びそうになっても、傘を握りしめたまま、バッグも手放そうとしないものだから。
両手ふさがりという、ある種の「無武装」を強いられるのは、決して雨のせいではない。傘と鞄を持たねばならない己の必要性ゆえの出で立ちである。
傘と鞄で両手がふさがったまま某所に出掛けて帰ってくるだけならいいが、切符を買う、ICカードを使う、財布を出し入れする、濡れた手をハンカチで拭いてスマホを取り出す……などの動作が伴う。雨の日に傘の置き忘れが多いと聞くが、あれはビニール傘よりも重要なものを守ろうとするあまりの結果だと睨んでいる。
人は「雨の日の傘と鞄」という出で立ちに似た生き方を標準とする。両手がふさがって、片手の余裕のない生き方。もう一つ荷物が増え、もう一つ外的変化を考慮すべき状況になると、それこそ「手に負えなく」なる。
今のところ、両手ふさがりが「八方ふさがり」になると断言する確証はないが、持たねばならないもの、しなければならないものを常日頃見直しておくのがよさそうだ。