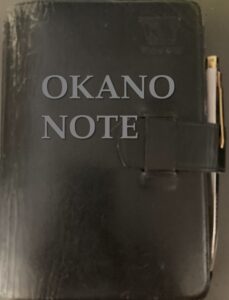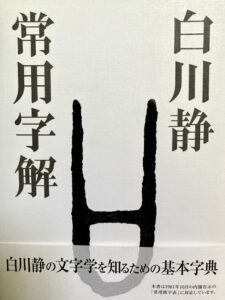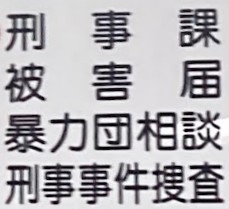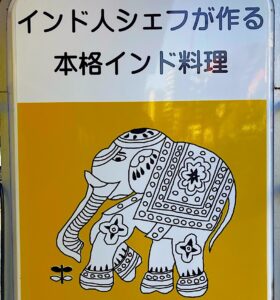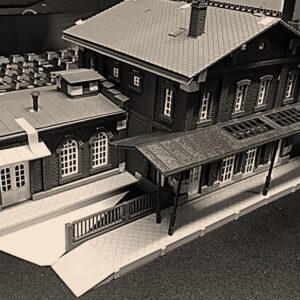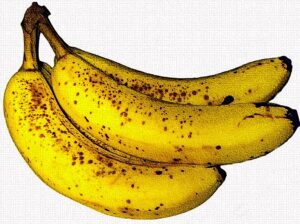本ブログ、“Okano Note”は今日のこの投稿で2,000回を数える。何かシャレたことを書いてみようと思ったが、平凡に17年2,000回の雑感を綴ることにする。
2,000回の一つ前に1,999回があり、2,000回の一つ後ろに2,001回がある。こうして見ると、2.000回が他の回と同じく一つの通過点であることがわかる。どういうわけか、1,000回や2,000回を区切りにしようとするのが人の常。しかし、「ちょうど100」と言うのもあれば、「ちょうど257」と言うのもある。
「ちょうど」というのは人間界で人間が作り出している。誕生日が12月25日の人が買物をして1万円札を渡した。お釣りが1225円だったら、ぴったりちょうど感を覚える。ただそれだけのことだ。ブログの2,000回は数えていたのではない。投稿一覧に投稿回数が出るから知っただけのこと。
徒然なるままに文を綴るにしても、動機も無しに週2回ペースで続けることはできない。動機の内容が同じだと来る日も来る日もよく似たことを書かざるをえない。飽きないように長く続けるには多様な動機がいる。多様な動機が多様なテーマのヒントを授けてくれる。
サービス精神のつもりでも説明が過剰になると嫌がられる。親切心で綴っても、小難しい文を読む他者には迷惑なことがある。饒舌に要注意だ。しかし、思いつきの短文を適当に書いてけろりとしているわけにはいかない。公開とは責任を負うことなのだから。
「継続は力なり」と言うけれども、何の力なのかが明らかにされない。ずっと続ければいったいどうなるのか……継続は力なりの「力」は、続けるという力である。つまり「継続は継続する力をもたらす」の意。そう、この言い回しは同語反復にほかならない。
書いた文章を照れもせずに抜け抜けと公開しているわけではない。自分の書いたものを他人様にお読みいただくのは、内心うれしくもあり、また自信にもつながるのだが、内実の心境としては少々気が引ける。17年経った今も少々恥ずかしい気持に変わりはない。書いたり話したりすることには照れがつきまとう。
これからも、考えることや気づいたこと、その他諸々の見聞を――書かないよりは書いておくほうがいいと判断して――公開していこうと思う。衒学に走らず、また自己陶酔に陥らないように気をつけて。