 旧暦の神無月は新暦でも使い、グレゴリオ暦の10月と併用すればいいのに……と思ったことが二、三度ある。
旧暦の神無月は新暦でも使い、グレゴリオ暦の10月と併用すればいいのに……と思ったことが二、三度ある。
 今月は、厚切りベーコンとたまねぎのトマトソースパスタ、牛肉スープにつけて食べる和蕎麦のつけ麺、パクチーお替り無制限のフォーなど、麺の当たり月だった。「麺月」と呼んでもいいくらいだ。
今月は、厚切りベーコンとたまねぎのトマトソースパスタ、牛肉スープにつけて食べる和蕎麦のつけ麺、パクチーお替り無制限のフォーなど、麺の当たり月だった。「麺月」と呼んでもいいくらいだ。
 コピーライティングの仕事が多かった。そのうちの一つに、何を書くかはほぼお任せというミッションがあった。
コピーライティングの仕事が多かった。そのうちの一つに、何を書くかはほぼお任せというミッションがあった。
「始まりは心弾む予感に満ちて」という見出しを思いついた。そして本文の一行目に「一つの季節の終わりが次の季節の始まりにバトンを渡す」と書いた。
何を書くかを考える前にことばを綴ったら、原稿用紙一枚分がまずまずうまく、さっと書けた。考えるだけが能ではないことにあらためて気づかされる。仕事を続ける効能の一つ。
 とある和食店は毎日一種類のランチ提供を貫く。店の前のホワイトボードには「天然ぶりの刺身とはまちの煮付け」と書いてあった。ぶりとはまちの出世魚定食? パスした。
とある和食店は毎日一種類のランチ提供を貫く。店の前のホワイトボードには「天然ぶりの刺身とはまちの煮付け」と書いてあった。ぶりとはまちの出世魚定食? パスした。
 リバーサイドの夕暮れ、川面の濃紺と紅。清濁併せ吞む大阪の繁華街には、古都では出合えない、侮れない風景が時々浮かび上がる。
リバーサイドの夕暮れ、川面の濃紺と紅。清濁併せ吞む大阪の繁華街には、古都では出合えない、侮れない風景が時々浮かび上がる。
 その数日後、難波ゆかりの万葉集をテーマにした展示を見た。古代にも侮れない大阪があったことを知る。
その数日後、難波ゆかりの万葉集をテーマにした展示を見た。古代にも侮れない大阪があったことを知る。
昔こそ難波田舎と言はれけめ今は京引き都ぶにけり
「昔こそなにわは田舎と言われていたが、今は京の様々なものを移してきたので、いかにも都らしくなった」というほどの意味。「垢ぬけた」ということだろう。
 9月末から、行きつけの野菜のセレクトショップに旬の落花生が出始めた。生の落花生を半時間ほど柔らかすぎず硬すぎずに茹でる。毎週二、三回、実によく口に放り込んだ。
9月末から、行きつけの野菜のセレクトショップに旬の落花生が出始めた。生の落花生を半時間ほど柔らかすぎず硬すぎずに茹でる。毎週二、三回、実によく口に放り込んだ。
 来年2月にグランドオープンする大阪中之島美術館。建設の様子を見てきた。開館から春にかけては岡本太郎、モディリアーニが予定されている。黒のエクステリア。少し歩くと対照的な赤。愉快でキュートだった。花の写真はめったに撮らない。つまり、撮った花の印象はなかなか忘れない。
来年2月にグランドオープンする大阪中之島美術館。建設の様子を見てきた。開館から春にかけては岡本太郎、モディリアーニが予定されている。黒のエクステリア。少し歩くと対照的な赤。愉快でキュートだった。花の写真はめったに撮らない。つまり、撮った花の印象はなかなか忘れない。

 高知産の新生姜をスライスして生食したら、嘘のように翌日シャキッとした。二箱が無料のあの「しじみ習慣」も嘘のようにシャキッとするのだろうか。
高知産の新生姜をスライスして生食したら、嘘のように翌日シャキッとした。二箱が無料のあの「しじみ習慣」も嘘のようにシャキッとするのだろうか。
 一昨日から読み始めたのでたぶん来月にまたがるが、古本屋で買った『なんだか・おかしな・人たち』(文藝春秋編)がなんだか・おかしい。渋沢栄一を父に持つ渋沢秀雄の「渋沢一族」という小文は、他の渋沢像と違った見方でおもしろい。渋沢栄一は明治24年に87箇条の「家法」をしたため、第一条で渋沢同族を次のように限定している。
一昨日から読み始めたのでたぶん来月にまたがるが、古本屋で買った『なんだか・おかしな・人たち』(文藝春秋編)がなんだか・おかしい。渋沢栄一を父に持つ渋沢秀雄の「渋沢一族」という小文は、他の渋沢像と違った見方でおもしろい。渋沢栄一は明治24年に87箇条の「家法」をしたため、第一条で渋沢同族を次のように限定している。
「渋沢栄一及ヒ其嫡出ノ子幷ニ其配偶者及ヒ各自ノ家督相続人」
同族から誰か貧困の者が出ると「子孫の協和」が保てなくなるため各家の生活を保障するシステムを作った。渋沢一族という「組織」にあっては、長男以外は兄弟姉妹が男女同権で平等に栄一の恩恵を受けることができた。私企業の利ではなく国家、社会の利を強調した栄一も、同族を末永く保持することにかけては細やかな神経を使っていたのである。











 ちゃんぽんを売りにしている中華料理店のホール担当は、小柄なおばさんで年齢はおそらく
ちゃんぽんを売りにしている中華料理店のホール担当は、小柄なおばさんで年齢はおそらく


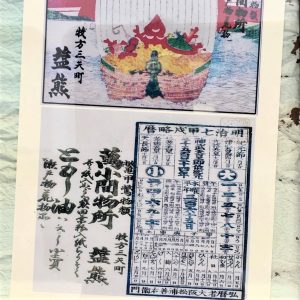

 共用スペースにつき、マスク着用のない会話はお控えいただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
共用スペースにつき、マスク着用のない会話はお控えいただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
