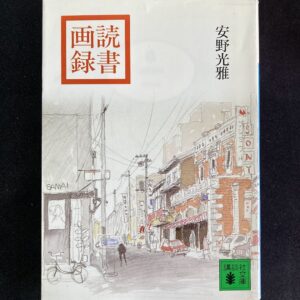芸術の季節と言えば、通り相場は「芸術の秋」だが、たとえば「美術の春」があっても不思議ではない。春にどこかに出掛けて風景を眺めたり街中でたまたま展覧会の前を通り過ぎたりする時、美術の春を想う。春に目に入ってくる対象は明るい水彩画のモチーフになる。
ゴールデンウィークは近場に出掛けてよく歩いたが、どこの美術館も要予約。行き当たりばったりでは入館できない。と言うわけで、絵画に関する本で美術不足を補った。もっぱら鑑賞側の愛好家だが、久しぶりに絵筆をとってみようという気になっている。
🖌 『読書画録』(安野光雅)
いわゆる画家が、自分を芸術家だと信ずるために、看板絵などを軽く見ることのすくなくなかったそんな時代に、場末の風俗や、安花火や、果物屋の店頭に、時代に先んじて美しさを発見し、
――つまりは此の重さなんだな――
といわしめる一顆の檸檬を絵にしたのである。
画家である安野は梶井基次郎の小説『檸檬』を読んで、この作品を絵だと思ったと言う。小説の読後の感覚と絵画鑑賞の感覚に同等の感動を覚えたのだ。本書の表紙は安野自ら描いた京都三条と麩屋町の交差するところ。すぐ近くに丸善があった。当時、『檸檬』を読んでその余韻を求めてやって来た人が多かったはずと安野は思う。
🖌 『絵はだれでも描ける』(谷川晃一)
(……)上手な絵だけが絵画ではないし、上手ということがそのまま見る者を感動させるとはかぎらない。むしろ上手に描くことによって真の魂の創造的表現力が失われることもめずらしくないのである。
ここでいう「創造的」とは何か。(……)「創造美術教育」のリーダー的存在であった久保貞次郎は(……)創造的である作品の特徴を次のように分類している。
1、概念的でない。
2、確固として自信にあふれている。
3、生き生きとして躍動的。
4、新鮮、自由。
5、迫力があるか、または幸福な感情にあふれている。
上手でなくても絵の好きな児童が描く創造的な絵はおおむね上記の5つの特徴を満たしている。他人に認められるモチーフや技を過剰に意識し始めると条件からズレてくる。モチーフについては次の一冊が参考になる。
🖌 『千住博の美術の授業 絵を描く悦び』(千住博)
画家の場合、モチーフとの出合いは一生を左右します。だから私は、モチーフは自分で得たものではなくて、「与えられたもの」だと思うのです。従って、少し描いて飽きた、とか、一枚描いたらもう繰り返し描かない、などというのではなく、何枚でも何枚でも描くのです。
イタリアのボローニャに旅した折り、市庁舎内でジョルジョ・モランディの常設作品展をじっくりと見た。モランディは主に卓上静物というテーマに生涯取り組み、同じような作品を次から次へと生み出した。しかも晩年はボローニャから外には出ずアトリエに閉じこもって創作を続けた。どれも似たり寄ったりで、あまり好みの筆遣いではなかったが、記念に10枚1セットの絵はがきを買った。買った当時よりも今のほうが気に入っている。モチーフに憑りつかれてこそ生まれる画風の個性なのだろうか。