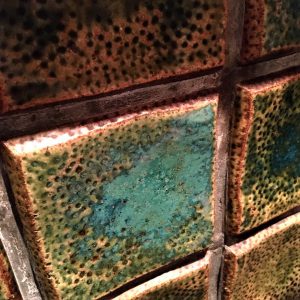散策をテーマにしたコラムを依頼された。「川岸の樹々の移ろいに気づく秋。暑さから解放されて一息つける今なら、遠くの野鳥のさえずりも枝葉のそよぎも聞こえてくる」と書き始め、ふと思う。川岸も樹々もさえずりも四季を選ぶわけではないが、どういうわけか、秋との相性がいい。ある日の街歩きを思い出した。

セーヌ川に沿ってエッフェル塔に近づき、シャン・ド・マルス公園の落葉絨毯の上を踏み歩いた。秋はほどよく深まり、物語が始まりそうな気配が漂っていた。いや、ある散策者にとっては物語の終わりだったかもしれない。あの歌詞のように。♪ 枯葉よ~
名詞には意味が備わる。音が刻まれる。意味と音が重なり合って色が見える。「秋」には意味があり、“aki”という音があり、そして色がある。こうして秋は、春や夏や冬との差異を感知させる。
ボードレールに「秋の歌」という詩があり、その一節に「きのふ夏なりき、さるを今し秋!」(堀口大學訳)というくだりがある。別の表現もある。「昨日夏なりき、今し秋」(斎藤磯雄訳)。「昨日で夏が終わり、今日から秋」というわけだが、実際はこんなふうに時系列的に感覚がシフトするのではない。今日秋を感じたから、昨日夏が終わったことにしたのである。
近年、秋が短くなった。少なくとも、短く感じるようになった。遅れてやって来て足早に去る秋。去る前に早めの名残りを惜しんでおくのがいい。出会った次の日から送別会のリハーサルが始まる。
秋の夕焼けは美しい。日が暮れなずみ、やがて夕焼け空になる頃、メランコリックになる人がいる。ぼくの場合は昼食を軽めにしているので、夕焼け頃になると空腹が先に来る。精神的作用を催す夕焼けよりも生理的作用を刺激する夕焼けのほうがつねに優勢である。
今年特有のキャンペーン、いよいよ“Go to Eat”が本格化した。価格が25%分還元されればそれだけ過食になりかねない。豊穣の秋はご馳走の過剰に注意。名前の長さに比例してカロリーが高くなる料理がある。これまで出合った一番長い料理名は「地産ポークと有機無農薬野菜のガーリック炒め、小野さんのレモンイエロー有機卵の半熟目玉のせ」。文字数の多さに比例してガッツリ系だった。