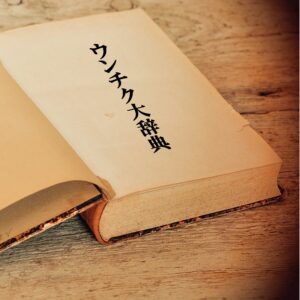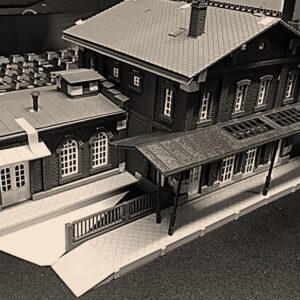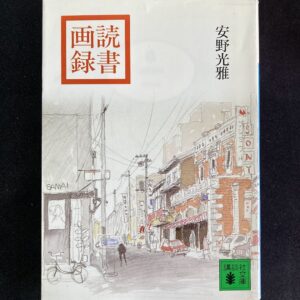蘊蓄とは「十分に研究を積んで蓄えてきた、学問や技芸上の深い知識」のこと。蘊は「積む」という意味であり、畜は貯蓄に使われる通り「たくわえる」である。
「あの人は熱心に蘊蓄を語る」と言えば褒めことば。ところが、蘊蓄を「ウンチク」とカタカナにすると小馬鹿にした感じに変わる。一般的には「蘊蓄を傾ける」という連語を使うが、これを「ウンチクを垂れる」と言い換えると、これまた皮肉っぽく響く。「ぐだぐだとウンチクするよりも他に時間を割くべきことは山ほどあるぞ」という意味が言外に潜む。
蘊蓄よりも重要なことは世におびただしい。蘊蓄を有り難く拝聴するというケースは稀で、いつ終わるかもわからない専門の知識を滔々と語られるのは嫌がられる。知識や学問を蘊蓄してきたことと、それを披瀝することは同等の価値とは認めてもらえない。
しかし、蘊蓄を傾けることによって、語る側も聴く側も知識の深みと広がりに気づくこともある。ある特定の知識の知識全体におけるディレクトリー(場所や階層)が見えてきたりする。蘊蓄に付き合わされる側はつらいが、誰かを捕まえて蘊蓄を傾けるのは悪くない。知っていることを誰かに語るというのは究極の知的トレーニングなのである。
高齢者が同じ話を延々とし始めたら、「あ、脳のトレーニングをしているんだな」と鷹揚に構えて聞いてあげるのがいい。