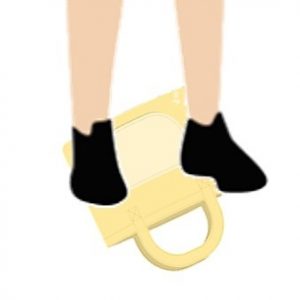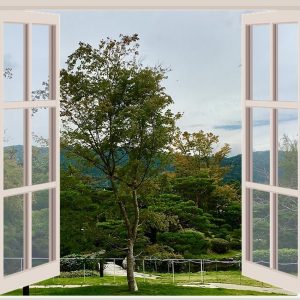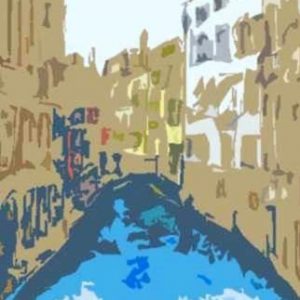近くの川岸が夕方になるとほのかに橙色を帯びる。もしかして桜? と早とちりする人がいるが、十日以上早いからさすがに桜はない。実はライトアップ。ライトアップが春のフェイントをかけているのだ。
春本番を控えて景色がフェイントをかける、気配も気候もフェイントをかける。フェイント(faint)は「かすかな」ということ。かすかであるから一時的に春らしくなっても、すぐにらしさは消えて、また肌寒くなったりする。三寒四温とは、冬から春に移り変わる時期の言い得て妙である。
散歩中に、右へ曲がりかけて、ふと気が変わって左へと踵を返すことがよくある。冬色と春色が境界なく混ざるような配色も目に入る。焦点が定まらず、身体も適応し切れず、気持ちはいいのだが少々気だるくふわっとする午後の時間がある。
今年こそやるぞ! 旅に出るぞ! 本を読むぞ! 趣味に勤しむぞ! などと毎年同じことを決意表明する者がいる。必ずしも他人事と言って片付けられないが、あれもフェイントの一種である。自分を宥め欺き、決意をきれいさっぱり忘れるために欠かせない一人フェイント。
人生は大小いろいろなフェイントの連続。時には一人で、時には集団で。フェイントは自分を、他人を惑わせ続ける。そして、フェイントであったことがばれる。フェイントのフェイント、それに次ぐフェイント、そのまたフェイント……フェイントはフェイントを呼ぶ。