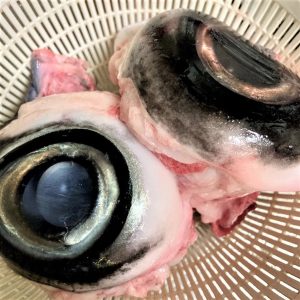まぐろの刺身と天ぷら3品をつまみにして生ビール1杯だけのつもりだった。生ビールを飲み干そうとした時、ふと見た壁の貼り紙に「イカのわた焼き」を見つけた。イカは好物で、わたと絡めた焼いたイカなら言うことはない。追加で注文し、これに合いそうなのを地酒の夏メニューから選んだ。岐阜の「涼」がそれ。
そろりと一口すすり、アルミホイルに包まれた熱々のイカ焼きを一切れ頬張る。二口、三口すすった頃にホールの女性が席に来て、「こちら翠になります」と言う。テレビでも宣伝していて、いま少しはやり始めているジンのソーダ割りだ。注文していない。と言うか、この女性、今しがたぼくに涼を届けたばかりである。
「翠? 注文してないよ」と言ったぼくの声が近くのオープンキッチンに聞こえたのか、厨房の男性スタッフが「そちら涼ですよね?」と確認する。酒を指差して「そう、これは涼」とぼく。ホールの女性は「すみません。間違いました」と謝る。ただこれだけのことだが、注文確認のぎこちない様子を見ていると、これで一件落着とは思いづらい。
ぼくが涼を注文し、ホール担当が「こちら涼です」と言ったから、いま飲んでいるこの酒を涼だと思っている。何かのミスで、仮にこの酒が一ランク下の普通の清酒だったとしても、言われるがまま涼だと思うしかない。かなりの飲み手でないかぎり、味の判別はできそうもない。何よりも涼なる酒を飲むのはこの日が初めてだ(いや、何度か飲んでいたとしても、並の清酒との違いがわかったかどうかは疑わしい)。
この初めての酒をゆっくり味わいながら、何口か飲むうちに、この酒が最近飲んだ新潟の地酒と違うことが少しずつわかってくる。「松○梅」と違うこともわかる。わかるが、だからと言って、この酒が涼という確証はない。別の酒が誤ってぼくに運ばれたとしても、「これは注文した酒ではない」と言えるほどの利き酒はできない。この酒が涼とされるのは、ぼくがそれを注文し、店が涼と告げたからにほかならない。
日本酒は稀にしか飲まないが、これまではほとんどの場合、目の前で一升瓶からグラスに注がれたはずである。注文した銘柄と一升瓶のラベルを照合して飲んでいた。イカのわた焼きは正真正銘のイカだったが、すでにグラスに注がれて運ばれてきた酒が、間違いなくぼくの注文した銘柄であるかどうかはわからない。日本酒よりも少しはわかっている赤ワインでも同じだろう。
この話に結論はない。一つ言えるとすれば、酒の味わいの大部分は名の味わいであり、名と味を照らし合わせて楽しんでいるということだ。ところで、あの地酒は何だったのか? 常連ではないが、行けば安くていい料理を出してくれる。それが信頼というもので、イカのわた焼きに合わせたのは注文通りの酒に間違いなかったと思っている。