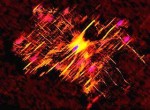神々の論争
神々と人々、人々と他の生き物たちを分け隔てているのは何であるか、実はよくわかっていない。神、人間、他の生き物という序列に確定的な根拠など何もない。神は人間よりもはるかに優れているという定説があるが、人間と他の生き物とは紙一重の差だと言われることもある。
神々の世界には時間の観念がない。したがって過去も未来もないから、歴史が存在するはずはなく、つねに現在のみが進行している。人間の尺度でははるか太古の話のようであっても、神々の世界では出来事も神話も普遍である。

蠅が神話世界の城市に棲みついて神々を大いに悩ませていた。神殿にまで神出鬼没しては耳障りな翅音を立てた。神々のことである、およそ大抵のことは神通力で何とか対処できたのだが、この小生意気な蠅どもには功を奏さず、それどころか、蠅どもは神々の焦り疲れるのを嘲笑うかのごとく自在に生を謳歌していた。わが物顔で振る舞う蠅は天下の一大懸案となった。ある満月の夜、壱の神は策を練らねばならぬとついに決断し、重鎮の神々を本城に招集した。
「われらが城市は湿潤温暖の気候にあるがゆえ、生命にとっては好都合なようで、近頃蠅どもがおびただしく発生しておる。汝らの力も及ばず、大いに閉口していると聞いた。さて、そこでだ。ひとつ列席の神々に尋常ならぬ智慧を絞っていただきたくお集まり願った次第である。何か妙案はないものかのう」
弐の神が顎髭を丁寧に撫でながら口火を切った。
「心配無用。いや、実を申すと、かねてより案を練っておったところだ。殺生すれば容易に済む話なのだが、殺生はわれわれの本意であるはずもない。だが、双方――すなわち、われらと蠅ども――を同時に救う手立てがあるのだ。僭越ながら、この妙案は壱の神の御趣意に背くものではないと自負……」
話を言い終えぬうちに、焦れた参の神が割り込んだ。
「もうよい、わかった。早うその先を言わんか!」
「御意。一刻を争っている時に余計な前口上は控えていただきたいものだ」と四の神も語気を強くして続けた。
「まあ、そう急ぎなさるな。昨日今日始まった難儀でもなかろう。そもそもこのように蠅どもが繁殖したのも、参の神、汝の方に因があることを忘れなさるな」と、弐の神が反論した。
小魚が一斉に川面に現れたかのようにざわめきが起こった。
「弐の神よ。言を慎みなされ。過ぎたる事をぶり返すのは潔くない。今宵の集まりはそのような咎め立てを云々することではない!」と、参の神の派閥に属する五の神が追い討ちをかけた。あちらこちらがいっそう騒然としてきた。たまりかねたように六の神が制しようとした。
「見苦しいではないか。少々気を鎮めたらいかがじゃ。皆の心の内は分からぬでもない。だが、弐の神の一案を聞かずして、この有様では話にならぬ。壱の神よ、ぜひともこの場を取り収めていただきたい」
ところで、弐の神が言うところの「参の神の因」というのはこうである。蠅が湧き始めた頃、神々の間では早々に退治せよという意見と殺生に反対する意見が出た。殺生反対派を牽引したのが参の神であった。殺生せずとも、蠅は天井知らずのようには増殖しない……放っておいても大事には到らぬと、参の神は殺生派の神々を説得した。しかしながら、参の神の思惑とは異なり、蠅は増え続けた。その繁殖ぶりは神事に支障を来すに到った。見かねた壱の神が力を合わせて策を練ろうというのが、この集まりの趣旨であった。
さて、上気した顔をお互いに見合わせて神々は口々に異論や不満を吐き始めた。ほどなく堂々巡りが飽和してざわめきは徐々に消えて小声になり、やがて沈黙の時間が続いた。誰から合図するともなく、皆が壱の神の方に視線を向け始めた。
壱の神は大きく息を吸って、溜息を吐いた。深く刻み込まれた額の皺に掌を当てがって、しばらく黙っていた。皆の視線は熱を帯びて壱の神の口元に注がれた。それに応じるように壱の神はゆっくりと口を開いた。
「汝らよ。未だ聞きもしていない弐の神の腹案とやらがあるが、もうそれをもなかったことにしてはもらえぬか。と言うのも、先程からわしの耳元で数匹の蠅が唸っておる。この耳障りな音は何かを訴える声に相違ない。そう思い、汝らが静かになった直後から耳を傾けていたのだ。蠅も生き物だ。心があるようだ。驚いたことに、われらが神言を操るほどの賢さだ」
堂内はこれ以上ないと言うほど静まり返った。壱の神は続けた。
「これより先は世々代々に亘って神々に随い全身全霊で手を擦り合わせて生きていくゆえ、ぜひとも過ぎたるをお赦しくだされと申しておる」
神々は恥じらうように項垂れた。目線を落としたまま、両手を合わせて膝の上に置いた。互いに見られぬよう用心しながら、右手は右の太腿の上で、左手は左の太腿の上で、それぞれ微かに手を前へ後ろへと動かし始めた。神々の動作はまるで蠅のようであった。
神々と蠅には聖なることにかけては雲泥の差がある。しかし、事を顧みて自省の念にかられる時の動作は酷似している。神と蠅の位置取りにしてこうであるから、神と人間の差などは、あるようで実際は無いに等しい。当たり前だろう。一応神が神を模して人間を作ったという説が有力なのであるから、似ていないはずがない。今も人間世界では論議や審判をおこなう前に「神に誓う」習わしがある。これは神とそっくりのやり方をするという誓いにほかならない。
岡野勝志 作 〈1970年代の短編習作帖より〉