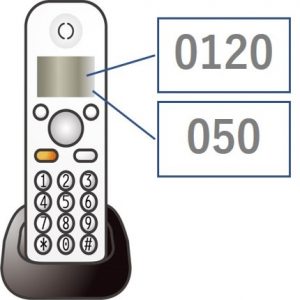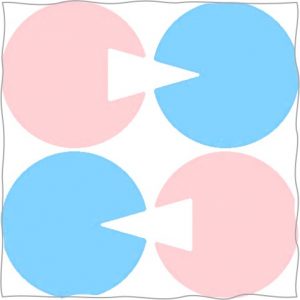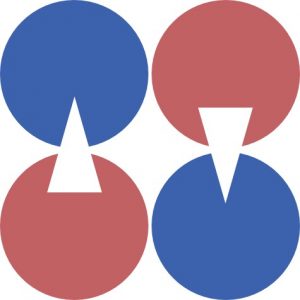「たちはたらく」とあれば、「たちは/たらく」とか「たちはた/らく」とか「たち/はた/らく」ではなく、たいてい「たち/はたらく」と読む。では、この「たち」の漢字はどうか。これも、達、舘、質、太刀などとひねることはなく、おそらくシンプルに「立ち」と想像して、「たちはたらく」を「立ち働く」と突き止めるはずである。
この「立ち働く」ということばが読んでいた本に出てきた。自ら使ったことはない。どこかで見たような気がしないでもないが、めったにお目にかかれない表現だ。この立ちが「立っている」という意味でないことはわかる。その場にじっと立っているだけでは稼ぎにならない仕事もある。「小まめに働く様子」が浮かぶ。念のために辞書を引いてみた。
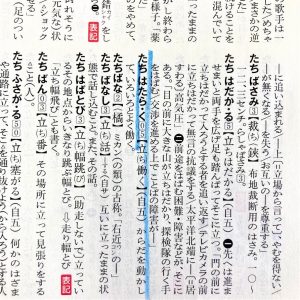
「立ち」は接頭辞である。これが付く動詞は少なくないが、「身体的に立つ」という意味を持つのはわずかである。「立ち――」は「実際に――する」というニュアンスを感じさせる。
「あの人は立会人のくせにずっと座っていた」などといういちゃもんは成り立たない。立会人の仕事は終始立つことではない。席に座っていても立ち会うことができる。実際にその場にいることが重要で、立っているか座っているかは問題ではない。バーチャルではなくリアルに臨場することが立会人の果たす使命である。
「立ち勝る」という表現もある。単に「優れている」とは違う。「立ち」は、その後に続く行動・行為の一途さを強調する。何もかもが勝っているのだ。断然で圧倒的で決定的な勝りようであり、その立場は現実には覆りそうもない。大きくリードした九回裏に易々と逆転されることもない。
立ち至る、立ち返る、立ち向かう……いろんな表現がある。「立ち至る」は、「重大な局面に立ち至った」と使うように、予測ではなく、現実になる状況を示す。「立ち返る」は、体操の技ではなく、もと居た所や出発点に戻る意にほかならない。敵に立ち向かうのなら、覚悟して本気で掛かっていかねばならない。ある方角に赴くという意味の「向かう」とは一線を画しているのだ。