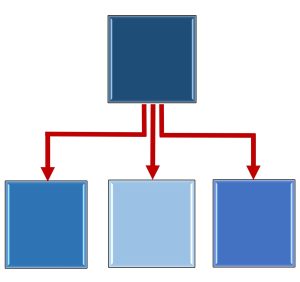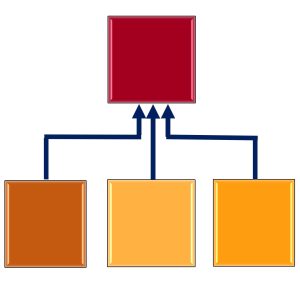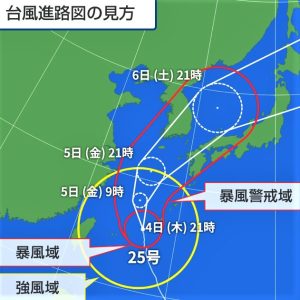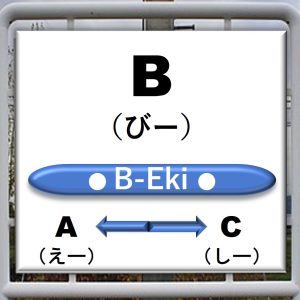「暑と署」を書き間違いする成人を見受けるが、「暑」は小学3年生で教わる漢字という。よく見ると、上から下へ「日+耂+日」という要素で組み合わされている。この一字がいかにして「気温が高い」という意味になったのか。
「日」は太陽である。太陽の下に柴の意の「耂」があり、それがもう一つの「日」の上に積まれている。者は「煮」に通じている。上からも暑く、下からも熱い。大暑、極暑、炎暑など並べて声に出してみると、見た目も響きも焼きつきそうな熱を感じさせる。
暑中見舞や残暑見舞のハガキは減っているが、今年もいろいろ届いた。一枚一枚あらためて眺めていると、暑の文字が体感温度を少しずつ上げていく。7、8年前だったか、三重県のセミナー担当者からいただいた、松阪牛を象った礼状兼暑中見舞が記憶に残っている。ペーパーの松阪牛に続いて暑を制する焼肉用の松阪肉の宅配を期待したが、届かなかった。
暑をエアコンで宥めようと頑張ると闘争になってしまう。人が暑と闘っている図が浮かぶ。近年は一夏を過ごすために暑を打ち負かさねばならなくなった。今ほど激暑でなかった半世紀前までは、「冷やす」という高コスト手段ではなく、「涼をとる」という省エネが夏の過ごし方の標準だった。
風鈴、かき氷、団扇、西瓜、夕涼み、打ち水、金魚すくい……。これらは夏に勝つ手段と言うよりも、今風に言えば「ウィズコロナ」に近い。「ウィズ暑さ」という共存の知恵である。
先週末「金魚すくい飴」という飴が売られていたので、一袋買い求めた。封を開けて舐めなくてもいい。これは涼をとるささやかな工夫である。昨日は処暑だった。暑さが峠を越して朝夕に涼風がそよぐというのは昔の話。二十四節気の暦を鵜のみにしてはいけない。