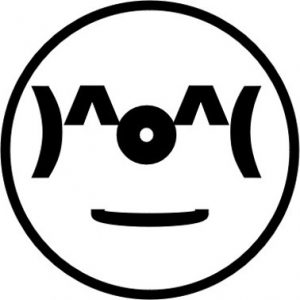「名付け」を英語にすると「ネーミング(naming)」。ネーミングを日本語に訳すと名付け。同じ意味だが、使う場面に違いが出る。名付けは対象を特に選ぶことなく命名一般に使う。他方、ネーミングのほうは商品やブランドの名前に使われることも多く、消費者への印象付けを意識するところがある。
『古事記』は名付けの例の宝庫である。誰それがこうしたというエピソードにちなむ地名が詳細に書かれ、史実らしきものも多々あるが、駄洒落やことば遊びと思われるものも混じっていそうだ。そもそも苗字の命名は土地とその地形的特徴に由来し、山や田や村、川や森や野などを含む姓などは必然おびただしくなる。
最初にことばが生まれた頃は、何らかの〈音〉と〈もの〉が、特に規則性もなく、たまたまくっついたと思われる(但し、人間にとって発声しやすい音だっただろう)。ともあれ、名とその名で表されるものの関係は恣意的であった。つまり、犬を「ネコ」と命名しても、猫を「イヌ」と命名してもよかったのである。
ほとんどのものがまだ名を持たない時代と違って、名の付かないものがない現代では新しく生まれるものに創作的な名付けがおこなわれる。既存のものとの差異をはっきりさせるために、また、コンセプトを定めてそれに見合うように名前が考えられる。コンセプトを象るような表現が名付けされることもあれば、コミュニケーションを意識した表現でネーミングされることもある。
ものの名を知らないなら、もの自体もたぶん知らないだろう。いや、ものは見たことがあるかもしれない。しかし、見ていたとしても名を知らなければよく知っていることにはならない。名が不明不詳だと目の前の「それ」に不安を覚える。知らなければ信頼しづらいし、「それ」についての情報もうまく共有することができない。
Xに名付けするとは、同時にYやZと差異化することでもある。Xだけに名前があってYとZになければ、その三者間において名付けすることに意味はないし、名がないものとの差異化もできない。特に、「右」と「左」など、概念が二項対立的な関係の場合、今日「右」だけが名付けられて、明日「左」が名付けられるなどということはありえない。同時に名が生まれる必要がある。右は左によって、左は右によって明らかになる。相互にもたれ合って成り立っている関係なのである。
人の名前を知らなかったら、「すみません」とか「そこのあなた」などと呼びかけるしかない。名前を知らないと落ち着かないから、初対面の場では口頭で自己紹介したり名刺を交換したりするのである。一度も見たことのない人の話が出たとする。その人の名前が「〇山〇郎」であろうと「川□和□」であろうと何とも思わない。
しかし、指名手配犯になると話は違う。容疑者の名前がわかっているし写真もある。名前だけでも写真だけでも指名手配はやりにくい。名前と写真が一体となってこその手配書なのだ。姓名不詳の似顔絵やモンタージュの場合、姓名と写真の不足を補うための「50歳代の丸顔の男」という情報だけでは逮捕に協力するのが難しい。かつての「キツネ目の男」がそうだった。顔文字にほんのわずかなコメントを添えた手配書ではいかんともしがたいのである。つまり、人のアイデンティティには名とものとしての顔が欠かせない。