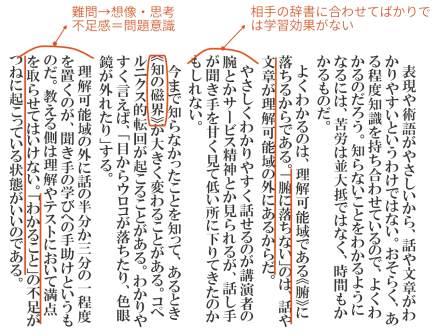昨日、何冊かに一冊は流し読みという読書に回帰しようと誓った。しかし、現実的にはそんな悠長な読み方は少なくとも仕事上は許されず、本にどんどん印を入れたり線を引いたり欄外にメモを書いたりする日々だ。
「線を引く」には二つの機能がある。後日の再読用に目立つようにしておく機能と、意識を高め読み取る気合を入れる機能だ。一つ目の機能は付箋紙でも代用がきくが、二つ目の機能はペンによる線引きでなければならない。印や線は内容の理解を促すような気がする。おそらく錯覚なのだろうが、ぼくの知り合いには一冊の本のうち90%の文章を蛍光マーカーで光らせている人がいる。
『広辞苑』で「下線」の項を引いたら、「アンダーラインに同じ」と書いてあった。ページを繰り直してアンダーラインの項へ。そこには「注意をひくため、または備忘のために、横書きの字句の下に引く線」とある。そりゃそうだ。文字の下に引く線だからアンダーライン。横書きの場合はそう。ところが、横書きの本なんて少数派ではないか。実際、手の届く本箱の一番上――読みかけやこれから読もうとセレクトした本を並べている棚――には80冊の本があり、そのうち横書きの本は『中学理科の教科書』と『ラテン語の世界』の二冊だけである。
わが国では圧倒的に多い縦書きの本。強調線を引くのは文字の右側であるから、アンダーラインとは言わない。ほとんどの国ではアンダーラインでいいだろうが、雑誌や一部の書物を除けば日本の出版物では下線の出番は少ない。再び『広辞苑』をめくった。さっき「下線」を調べたら「アンダーラインに同じ」だった。ならば、「横線」の項には「サイドラインに同じ」と出てくるのだろう、と推理した。
JR東海道線の支線「横須賀線」はあったが、「横線」なんていうことばはない。それで「サイドライン」へ飛んでみた。「テニス、バスケット・ボール、バレー・ボールなどで、コート両翼の区画線」が一つ目の意味で、二つ目に「傍線」とあった。
傍線なら知っている。傍点ということばもある。実を言うと、横線を発想する前に「縦書き文には傍線だろう」と見当をつけていた。しかし、ぼくが知るかぎり、傍線は自分のために引くのではなく読者のために引く線である。引用文などで「傍線筆者」と書くのは、読者のために原文にはない傍線を著者がほどこすことだ。
面倒臭くなってきたが、ここでやめたらそれまでの時間がムダになる。そこで念のために傍線を調べてみた。「強調し、または注意を向けさせるために、文字の横にひく線」とある(傍線部分は岡野――こんなふうに使う)。やっぱりそうだ。他人に向けられた線のことなのだ。しかし、ちょっと待てよ。強調するのは自分のためかもしれない。いや、自分が自分に注意を向けさせることだってありうるぞ。
というわけで、別の辞書『新明解国語辞典』にあたった。「縦書きの文章で、注意すべき字句(文)の右側に引く線」と定義されているではないか。さすが「明解(明快)」だ。これなら、注意すべき字句へ喚起させるのは自分でも他人でもいいことになる。しかも、「縦書き」と「右側」とまで厳密に書いてくれている。
縦書きの文章に引く線の名称は「傍線」ということで、一件落着。であるならば、先程の「強調し、または注意を向けさせるために、文字の横にひく線」の引用にあたっては、「下線部分は岡野」としなければならない。このブログ記事は横書きなので、必然下線と呼ぶべきであった。線はややこしい。縦書き・横書きに関係なく、これからは文章を囲もうと思う。