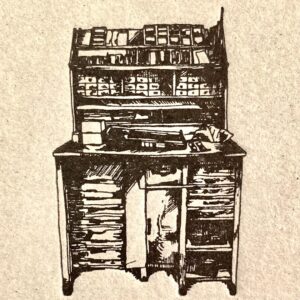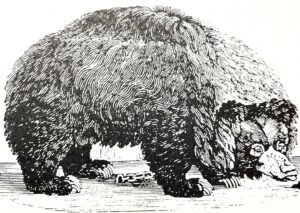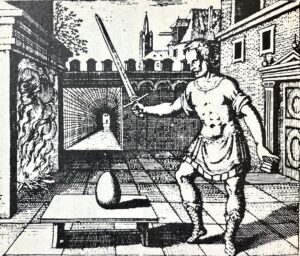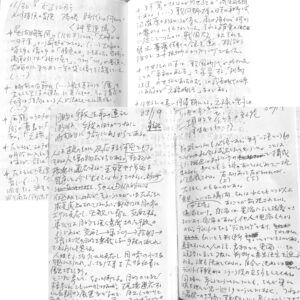20代後半に転職して広告・販促関係の仕事に就いた。最初は印刷会社が使う専門用語に戸惑った。自分が書いた文章にデザイン要素がレイアウトされて「版下」ができる。その版下が何のことかわからなかった。
版下とは写真製版用の原稿のことで、それを撮影して印刷の原板が作られる。先に用語が入ってくるから戸惑う。印刷会社の現場を見て説明を受ければさほど難しくない。なお、写真がなかった時代は絵を描き文字を書いた紙を反転して版木に貼り付けていたから、今に比べると手間がかかっている。
版と言えば版元、大河ドラマ『べらぼう』の蔦屋重三郎を連想する。あの作品は江戸時代中後期の出版社の仕事と時々の社会風俗を描いている。当時の版とは文字を書いたり絵を描いたりする板のことで、それに紙を合わせて刷った。
売れる本は同じ版を使って印刷部数を増やす。これを「版を重ねる」などという。重版出来も最初は読めなかった。「じゅうはんしゅったい」と読む。
本の奥付には「初版発行(第一刷発行)」や「第15刷発行」と記されており、辞書などは表紙にも「第五版」などと書かれている。英語では“version“や“edition“という用語が版のことを指す。
印刷や版画では技法のことを版という。おなじみの凸版、凹版、平版、木版、活版などが代表的。数年前にインクや紙の展示会に行った際に、印刷会社のショップカードをもらった。活版印刷された厚紙だ。凹凸感と質感の手触りが何とも言えず、今も捨てずに取ってある。活字だから活版、文字を使わず絵柄だけでも活版。紙の上で活きている。