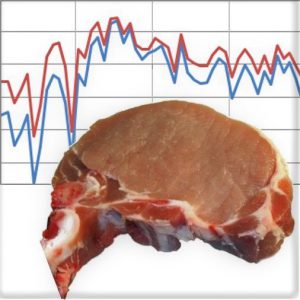靴下を買おうと、店じまいと貼り紙してある肌着のディスカウントショップに入った。「店じまい」の文字を目にしてから数年が経つ。アパレルの卸売りや雑貨問屋が多い土地柄なので、閉店セールを年がら年中やっている店が少なくない。閉店と謳いながら閉店しない店ほど目立つ。
店頭で店じまいを通知するが、ほどなく無事に閉店するのはごくわずか。ほとんどの店じまい宣言店は宣言後もずっと続く。これらの店では「店じまい」は「閉店しない」の同義語だ。「閉店を告げ、在庫一掃して安く売る」という恒常的な業態戦術である。これを閉店商法と言うが、万が一本当に閉まってしまうと逆に驚いたりする。
ギャグ①
「この閉店セール、いつまで?」
「うちが潰れるまでやりますよ」
ギャグ②
「閉店セール大好評につき、閉店は延期!」
ギャグ③
「お店、いつ閉めるの?」
「その時が来たらね」
ギャグ④
「毎週土曜日は閉店セール。年中無休」

本気で店じまいしようと安売りしたところ、話題になって客が殺到した。そんな日が毎日続いて、想定外の大きな利益が出た。閉店なんかしている場合ではない。こういう店は閉店を宣言したまま商売を続ける。「やめようと思ったし、今もそう思っているけれど、顧客満足優先です」。
冒頭のディスカウントショップでは、閉店セール中、レジカウンター内で社員がだいぶ先までの仕入れの話をしているのを聞いたことがある。やる気満々だ。
大阪に閉店セールで有名な店があった。何年どころではない。よく知る人によれば十数年ずっと「もうアカン!」という看板を掲げていたらしい。そしてついに閉店商法にピリオドが打たれ、正真正銘の店じまいの日がきた。大きなニュースになった。
コロナが蔓延して止みそうにない昨今、閉店商法はもはやギャグではなくなった。閉店セールの貼り紙は戦術ではなく現実なので、下手にいじることもできない。閉店商法華やかなりし日々は、ある意味でものがよく売れた平和な時代だったのである。