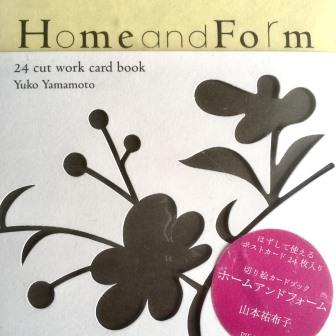加減とは調いと設えの状態を表わす。あることの具合が快ければ「良い加減」と言い、プラスの意味になる。しかし、「いい加減」となると意味はマイナスに転じる。おざなりで、でたらめで、中途半端なさまだ。
昨今将棋の人気が高まっている。おびただしい将棋ソフトが開発され公開されている。最上級のソフトは最先端の人工知能を搭載し、プロをも脅かすほどのレベルに達した。そのレベルには到らないものの、アマ上級者が太刀打ちできない無料ソフトがいくらでもある。先日、アマ二級~初段レベルのソフトを見つけ、指してみたら余裕で何連勝かした。将棋のルールが3ヵ条に要約されて説明されている。
1 王を取ったら勝ち
2 取った駒は好きな場所に打てる
3 敵陣に入ったら成ることができる
将棋を嗜む者にとっては、上記の3つのルールは説明されるまでもない。こんなルールよりもパソコン上での駒の操作のほうが重要だろう。他方、将棋の入門者はこの3つのルールを知っても将棋は指せない。何ヵ月か熟達者の指導を受けないと、このソフトが使るようにはならない。
1 たしかに王を取れば勝ちだが、王の取り方がわからない。自陣の駒の動かし方がわからなければ、王を取るどころか、敵陣にも入り込めない。
2 取った駒は好きな場所に打てる? いや、好きなマス目に必ずしも置けないのだ。飛車と角と金銀はどこにでも打てるが、敵の駒がある所に重ねて置けない。歩と香車と桂馬は盤の最上段には置けない。
3 敵陣に入ったら成ると言うが、この「成る」という意味が初心者には理解しがたい。成るとは駒が裏返って本来の能力をアップすること。なお、王は敵陣に入っても成ることはできない。
以上のように補足しても将棋は指せない。良い加減の説明が難しい。駒の動かし方は基本の基本だが、覚えてから将棋を指せるようになるまでの道のりが長いのである。そんな将棋を4、5歳までに覚え、小学生でアマ高段者の大人と互角に戦うようになるプロのタマゴの天才ぶりは驚嘆に値する。