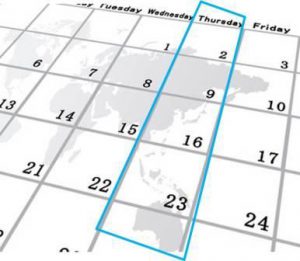昨日、あまりなじみのない場所に所用で行くことになった。スマートフォンでチェックすると駅から1.2キロメートル。タクシーを拾おうかと思ったが、行き先を間違う恐れはないし急ぐ必要もなかったから、歩くことにした。約15分。途中「タキシーメーター」と書かれた、年季の入った看板が目に入る。タキシードみたいに見えて可笑しかったが、誤字ではない。かつてタキシーメーターという表記が標準とされた時代があったのだ。
ぼくは車を所有したことがない。それどころか、運転免許証がない。だから、車を運転しない。徒歩か自転車か公共交通機関で移動する。これらの手段で賄えない場合はタクシーを利用する。タクシーにはよく乗るほうだと思う。タクシーに乗れば、タクシードライバーと狭い空間でしばらく時間を過ごすことになる。ドライバーは初対面の客に背中を向けている。よく考えてみると、異様な構図だ。いくら経験を積んだ人でも緊張感を免れないだろう。
対人関係の仕事は大変である。その最たる職業がタクシードライバーではないか。マニュアルではいかんともしがたい融通性が求められる。あの狭い空間で、水先案内、会話、金銭授受、安全配慮など一人何役もこなさねばならない。乗車から降車までのサービスに合格点を出せるケースがほとんどだが、それで当り前だと思っているからめったに感謝感激することはない。むしろ、気分を害した経験ばかりが悪い印象となって残る。善良なるタクシードライバーには気の毒な話だが……。
タクシードライバーと言えば、ロバート・デ・ニーロ主演の同名の映画を連想する。腐敗した街を、荒んだ心の人を浄化しようと行動する男の話。デ・ニーロ扮するドライバーは無口だった。喋り過ぎも困るが、無口はもっと困る。初対面の二人だけの狭小空間の数秒は恐ろしく長い。お喋りか無口かというのは変えづらい性格であるが、そのつどの相手によっても変わる。話題によっては無口がよく喋り、お喋りが黙ることになる。先日、関西有数の観光地でタクシーに乗った。「どうです、観光客は増えていますか?」と尋ねたら、「さぁ~」とドライバー(福原愛か!?) 客に仕事のことを聞かれて「さぁ~」はない。よろしい、そう応じるのなら、目的地に着くまで話し掛けないぞと決め、ずっと黙り通した。ドライバーのほうが沈黙空間の苦痛を味わったはずである。
十数年前の話。大阪の中心街Aでタクシーに乗った。ドライバーは40歳前後。当時住んでいた郊外のCを告げた。声が消え入りそうな生返事。走り始めて間もなく、「Cかぁ……Cねぇ……」とドライバーが独り言でつぶやく。しばらくして、また同じようにつぶやく。そうか、C方面への客を歓迎していないのだと察知する。こんなドライバーとあと半時間以上走るのはまっぴらだ。「Cに行っても帰りの客はないだろうし、行きたくないのなら、ちょっと先のBで降ろしてもらってもいい」と言った。瞬時に喜色満面になり、「そうなんですよ、Cは帰りがねぇ……」とドライバー。人生初のタクシー乗り継ぎとなった。
「ありがとう」も「すみません」もないので、リベンジだけして降りることにした。千円札を二枚渡し、釣銭を受け取る時にわざと取り損ねるという企み。数枚の硬貨が手のひらから落ちた。間髪を入れず、「おい、気を付けろ!」と威喝気味に叱責した。おとなしい客だと見てなめていたのだろうが、かなり怯えた様子がうかがえた。ドライバー、恐る恐る「すみませんでした」と言った。
降車したBのタクシー乗場へ移動して並ぶ。次は初老のドライバーだった。今しがたの一部始終を話したら呆れ果てていた。お客にも同業者にも迷惑をかける存在だと嘆いていた。ところで、その夜、めったにないことが起こった。タクシーに向かって手を挙げる人の姿が目に入ったのだ。「運転手さん、ほら、お客さんですよ」と言い、自宅マンションの手前だったが、そこで降ろしてもらった。客捨てるドライバーあり、客拾うドライバーあり。