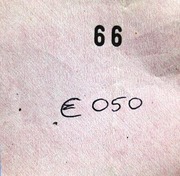料理を注文すると、注文を聞いた店員が「オーダー入りました」と厨房に告げる。「ご新規さま、ご注文いただきました」というのもあるが、店員が若い店では「オーダー」という言い方が目立つ。忙しくしている店員を呼び止めてぼく自らが「オーダーしていいですか?」などとは言わない。「注文していいですか?」か「注文を聞いてくれますか?」と、注文ということばを使う。
注文に相当する英語の“order”は多義語で、手元の英和辞典では名詞だけで21もの意味がある。もっともこれらすべてを覚える必要はなく、だいたい二つの原義さえわかっていれば文脈から意味を類推することはできる。一つ目は「順、秩序」という共通の意味を持つもの、二つ目は「命令、指令」という含みのあるものである。注文という意味のオーダーはこの二つ目から汲み取られたものだ。
オーダーに「注文」という日本語をあてがったのだが、オーダーそのものはある種の「命令、指令」であることに変わりはない。つまり、客であるぼくは「半トロ卵のラーメンと高菜ご飯のセット」が食べたいので、その商品名Cセットを店員に告げる。「Cセットを作って持って来い」と命令しているのである。店員は命令に従うのが使命であるから、厨房担当者に「Cセットというオーダーが入ったこと」を告げる。オーダーという注文にはオーダーという順番があり、客であるぼくに注文通りに運ばれたらオーダーという秩序が生まれる。そしてラーメンはオーダー通りに胃袋に収まる。こういう一連の流れが完了して金870円也が請求できるというわけである。
昨日のランチタイムはそのようになるはずだった。しかし、そうならなかった。ぼくに出されたのはラーメンAの単品。そのことを知るのは、Cセットについている高菜ご飯がなかなか出て来ず、店員に確かめた時点であった。ラーメンAがCセットのラーメンだと思い込んでいるぼくは、針金のような硬い麵を「変だなあ」と思いながら半分近く食べた。そこで店員をつかまえて聞いたのである。「これは高菜ご飯のセットでしょ? ご飯のほうがまだ来ていないんだけど……」。店員、確かめる。
すぐに高菜ご飯が運ばれてきた。食事再開ということで箸で麺をつまみ上げようとした瞬間、別の店員がラーメンを持って来た。「お客さま、お出ししたのはラーメンAでした。こちらのほうがCセットのラーメンになります」。と言うわけで、食べかけのラーメンが下げられ、熱々のラーメンが代わりに目の前に置かれた。100メートル走で50メートルまで走ってからフライングと告げられて、スタートラインまで戻された感じである。こうしてぼくは出来立てのCセットに向かい仕切り直しとなった。食べ終わったら超満腹だった。なにしろラーメンを一杯半食べたのだから。
接客マナーが重要だと言い、そのことについては、いかにも取って付けたような体裁ではあるが、まずまずできるようになった。しかし、客の欲しいものを厨房にリレーして、さらに厨房で作られた料理を注文した客に出すという基本は、マナー向上とは別のものである。その基本は一つのシステムなのであり、個の記憶と注意深さに関わるものだ。先日も、注文した焼肉が通っておらず、その後に頼んだ生ビールもなかなか出てこなかった。促されて初めて店員が気づくというケースは依然として珍しくない。伝言ゲームの多い店ほどその傾向が強く、そのつど紙に書いて✔印を入れている店ほどミスが少ない。