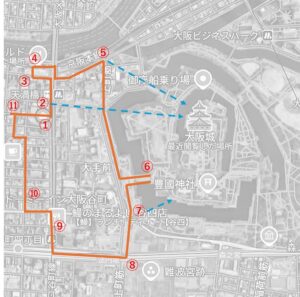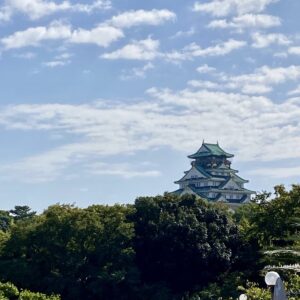かれこれ10年以上、毎朝小1時間ストレッチをしている。ストレッチの内容を体調に応じて変えたり、深い呼吸をするように意識している。これからも続けるつもりだ。やめたいと思ったことはない。また、嫌々やっているのでもない。つまり、ストレッチは惰性ではない。歩くのは1日平均8,000歩。これも惰性ではない。
これまでやって来たからという理由だけで、あまり考えもせずに続けてきた習慣があった。習慣形成しようと意識しない習慣もあったし、やめたいのになかなかやめられない習慣もあった。このような習慣は「惰性」と呼ぶべきものだ。
ほとんど何も考えずに、昨日今日と行為してきて、おそらく明日もそうするだろうという惰性的習慣の代表はコーヒーだった。手持ちぶさたになると、口には出さなかったが、「コーヒーでも飲むか」という感じで飲んていた。コーヒーを嗜んでいたつもりが、気がつけば惰性で飲んでいた。惰性でコーヒーを飲むのをやめてから、コーヒーがおいしくなった。日々のシーンでコーヒーの存在が大きくなり濃密な時間が持てるようになった。
惰性は急流に似ている。その流れに抗えなくなり意思や主体性を失うようになる。コーヒーの他には、テレビを見ること、本を買うこと・読むことが惰性になっていると気づいた。出社して朝一番に掃除したりコーヒーを淹れたりするのは意味のあるルーチンになったのに、PCにスイッチを入れて何げなく画面を眺める行為は相変わらず惰性のままだった。
惰性の最たる習慣がスマホの操作。惰性ではない朝のストレッチが小1時間なのに、惰性でスマホを触るのが2、3時間になってしまっていた。仕事のためや生活上の必要があって使っているのではない。スマホが趣味、スマホを使ってSNSを楽しむのはそれ以上の趣味というわけでもない。
生活のあらゆる場面から惰性を消すことは難しい。やむなく惰性に行き着く過程ではいろいろあったはず。コーヒーにも、突然の来客や打ち合わせなど、惰性にならざるをえない経緯があった。強迫観念や焦りから読書も惰性的になっていたかもしれない。
怠けて眠ってばかりいることを「惰眠」という。転じて、特段したいことがあるわけでもなく、また自らの強い意志で何かをするわけでもなく日々を過ごすことを意味する。適当に惰性的生き方をしてきたので、一気に「脱惰性的生き方」ができるとは思わない。それどころか、惰性とまったく無縁の生き方がどんなものなのか想像できない。
ともあれ、「他に価値ある選択肢があったのに、つい惰性的時間を過ごしてしまった」と、一日の終わりに振り返ることには意味がある。スマホとSNSの時間を減らしてから、惰性とそうでない行為・時間の違いを認識するようになった。毎日を同じものにしマンネリ化するのが惰性の本質。しかし、今日が昨日と同じ、明日が今日と同じではつまらないのだ。