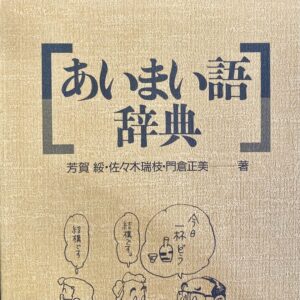月: 2024年12月
師走のプチ歳時記
ビール
芋焼酎のマイブームは昨年末から下火気味で、900mlの瓶は封を切らずに数本買ったまま。ワインは、1本飲んでは1本買うというありさまなので減ることはなく、相変わらず常時40本くらいある。セラーに入り切らないので一部は室温15℃の部屋に放置。冬だからこれで問題はない。そうそうオフィスにも10本保管している。
缶ビールは冷蔵庫に2、3本しか入っていない。あまり買い置きせず、飲みたい時にそのつど買う。暑い夏場よりも寒くなってからのビールがうまい。乾燥した部屋の中での最初の一杯で渇いた喉が潤う。缶ビールはそのまま飲まずにグラスに注いで飲む。しかし、缶ビールより瓶ビールのほうがいい。外食時もほぼ瓶ビール。生ビールはたまにしか飲まない。
そもそもビール党ではないので、痛飲することはない。週に1、2度中瓶を飲む程度だ。日本のビールは店で飲み、自宅ではたいていベルギー、ドイツ、チェコのビール。日本のビールとの違いはおおむね色が濃く、色のバリエーションが豊富だということ。
写真のドイツビールは飲んで初めて分かったが、アルコール12%というツワモノだった。グイグイ飲めないし、グラスでちびちび飲んでもほろ酔いの回りが早い。ほぼワインと言ってもいいほどのアタック感があった。
忘年会
昨日は3人だけのプチ忘年会。焼きとん酒場で午後5時スタート。飲み放題には関心がなく、3人で瓶ビール2本とハイボール1杯ずつ。串は1人5、6本、小皿のつまみが3皿、あとは枝豆と塩だれキャベツという質素なラインアップ。こんな飲み食いでも、雑談しながら2時間も経てばそれなりに満腹感を覚えるもの。
次の店はスナック。カウンターのみ9席の店だが、スペース感があって落ち着く。クリスマスイブ前の月曜日、客はわれわれ3人だけ。しばらくして、さすがに小腹が減ってきたので、1人がたこ焼きを買いに出た。1人にワンパック8個。昔はよくスナックでお好み焼きやたこ焼きを出前してもらったものだ。焼酎のお湯割りや水割りは各自2杯、歌は各5、6曲。ちょうどいいほろ酔い加減で午後9時半におひらき。2軒合わせてお勘定は5,000円ぽっきり。予算も時間の長さもシニアにやさしい企画だと自画自賛。
街歩き
冬になると、夏の1.5~2倍歩くようになる。歩き始める時は少し寒くても、1万歩も歩けばかなり温まる。距離と時間が長くなると、眺める対象も増えてくる。普段見えなかったものが視界に入りやすくなる。
御堂筋の歩道は、北上する時も南下する時もたいてい東側を歩く。よく動ける冬場は西側も歩く。すると、北御堂の歩道寄りの掲示板も目に入る。
このお寺のマスコットが「キタミゾウ」という象だと知る。「見たいゾウ、聞きたいゾウ、言いたいゾウ」と言ってる。まだ未熟ということなのか……「おさるさんってスゴイ!」のは、ゾウさんにできない「見ざる、聞かざる、言わざる」ができるからか……それは成熟のシルシなのか……ハイ、ここでストップ! 小難しく考えるのは厳禁。「おもしろいなあ」で止めておくのが街歩きのコツ。
慌ただしい年の瀬の二字熟語遊び
師走も早や終盤に入った。年賀状じまいという一大決心をして重荷を下ろしたが、雑用が増えて気分は慌ただしい。ブログを書き下ろす時間もあまりない。さぼらないように(また、鈍らないように)、夏場に書きためていた二字熟語遊びを年の瀬に捌いておきたい。
【里山 と 山里】
(例文)『桃太郎』のおじいさんが柴刈りに行った山は、山里ではなく、暮らしていた集落に接する近くの里山だった。
おじいさんは自然が残っている中山間地域の山に分け入って、焚き木用の小枝を取っていたのではない。そんな山里には行っていない。おじいさんが柴刈りをしていたのは、家から遠くない里山である。里山の山は低く、山里の山はそれよりも高い。山里にもわずかに人は住んでいたが、過疎地だった。「住む人もなきやまざとの秋の夜は月の光も寂しかりけり」という和歌が残っている。限界集落は今と変わらない。
【白黒 と 黒白】
(例文)「白黒も黒白も同じだよ」とえらく自信ありげに言う人がいたが、厳密にはそうではない。目は白黒させるが、黒白させることはない。
ややこしいが、是非や真偽については、「白黒をつける」でも「黒白をつける」でもいい。ところが、これまたややこしいことに、黒白をつけるという用例では黒白は「こくびゃく」と言うのが正しいらしい。読み方はともかく、白黒と黒白は互換性があるようだ。と言いかけて、白黒写真とは言うが、黒白写真とは言わないことに気づく。意味の重なりは一部あるものの、どうやら白黒と黒白は別物のようである。
【花火 と 火花】
(例文)それが線香であれ打ち上げであれ、花火がある所に火花が発する、飛ぶ、散る。他方、火花の元は花火だけではない。火花は目からも論争からも散る。
線香花火は手で持って愛で、打ち上げ花火は見上げて楽しむ。火がなくては花火は咲かないが、火がなくても散るのが火花だ。又吉直樹の芥川賞受賞作は、最初『花火』だと思っていたが、しばらくして話題になってから『火花』だと知った。書店でページを捲った程度で、作品は読んでいないからしかたがない。
〈二字熟語遊び〉は二字の漢字「〇△」を「△〇」としても別の漢字が成立する、熟語遊び。大きく意味が変わらない場合もあれば、まったく異なった意味になる場合がある。その類似と差異を例文によってあぶり出して寸評しようという試み。なお、熟語なので固有名詞は除外。
ことばに立ち止まる

知らなかったなあ、ソムリエがワインサービスの時に使う、左腕に掛けているあの布のナプキンの名称。知ったのはつい先週だ。「リト-」とか「トーション」と呼ぶらしい。世の中には知らないことが山ほどある。だから知らなくてもがっくりすることはないが、ナプキンと呼ぶよりはいい感じがする。覚えておこう。

たぶん7、8年前のこの時期だったと思う。冷たい風が吹く寒い日だったこと、公園脇の碑に菊池寛の座右の銘が刻まれていたことを覚えている。残念ながら、その座右の銘をすっかり忘れていた。そのことばを思い出したが、記憶を辿ったわけではない。別のことを調べていて偶然見つけたのだ。
不實心不成事 不虚心不知事
漢字を見て思い出し、「実心ならざれば事成さず、虚心ならざれば事知らず」という読み下し文で記憶がはっきりよみがえり、「現実的でなければ事を成就できず、こだわりを捨てなければ真実が見えない」という意味にえらく感心してノートに書いたことも思い出した。

なじみがあるのは「朝三暮四」で、手元の辞書では見出し語として出ている。ところが、「朝四暮三」は見出し語になっていない。知った時は、へぇ、そんな四字熟語もあるのかと少し驚いた。どちらも「目先の利益にこだわって、同じ結果だということに気づかない」という意味である。
飼っているサルに朝に三つのドングリ、夕方に四つのドングリをやろうとしたら、サルは怒って「朝に四つ、夕方に三つにしてくれ」と注文をつけた。一日で見れば同じ七つだが、サルには朝に四つのほうが得と思えた……という中国の故事。朝四つで夕方三つなら、あまり使わない朝四暮三のほうが本筋ではないか。しかし、朝四暮三と言ったりすると、「間違ってますよ」と注意されそうだ。

この字が店名に含まれている四川の中国料理店がある。「火へん」だから何となく想像できたが、辞書には載っていない。日本では使わない漢字のようだ。読めなくてもしかたがないが、どこかで見た記憶がある。とりあえず「火へんに考」で検索したら見つかった。「烤鴨」が出ている。ペキンダックのことで、烤は「カオ」と発音する。「烤魚」のほうは頻出語だ。魚の皮を焼いてからコトコトと麻辣味で煮る料理。直火で加熱する時は「烤」の字を使うらしい。
さて、ぼくの知るあの店は四文字。烤はわかったが、残りの三文字の発音ができない。店名が発音できたら一度行ってみようと思う。
語句の断章(60)勿体
「もったいぶる」という表現を使ったことはあるが、漢字で「勿体」と書いたことはない。本を読んでいて、もったいない、もったいぶるなど普通の表現として何度も出合っている。特に珍しいわけでもないのに、この漢字をずっと見ているうちに異化作用を催してきた。勿体? それはいったい何?
これまでどんなつもりで、もったいぶると言ったり書いたりしてきたのか。そもそも勿体とは何を意味しているのか。ある辞書には「物のあるべき姿や本質」と書いてある。どうやら、その意味がやがて「重々しい、立派、大きい、ものものしい、尊大とか威厳」に転じたようである。しかし……
ここまで書くのにいろいろ考えもし、調べもしておおよその意味とニュアンスは摑めたが、まだ「勿体」に慣れない。見れば見るほど、書けば書くほど、漢字変換すればするほど、奇異に見えてくる。もう一度問う、勿体とはいったい何?
奇異を拭おうと語源を調べることにした。次のようなことが書いてあった。
元は仏教用語で、勿体は「物体」と書かれていた。物は「牛へん」で、それは不浄な獣だから、へんを取って「勿」とした。勿体となって、物事の本質となり、ありがたみを意味するようになった。
おもしろい謂れだが、物から牛が消えて勿になったと言われてもすっきりしない。それで物事の本質となったら、なぜありがたくなるのかがわからない。
しばらくして、すっきりしない理由がわかった。「あの人は勿体だ」とか「事態は勿体になった」とは言わないのだ。つまり、勿体は単独で使わない用語なのである。
さほどでもないのに、ちょっと見に内容があるように感じさせるのは「もったいぶる」。まだまだ使えるのに無駄に粗末に扱うことやまったく使っていないのを惜しめば「もったいない」。気取ったりすまし顔したり、体裁を飾ってものものしく振舞って威厳を示すなら「もったいをつける」。
威厳などという立派な意味があるのに、勿体はその意味で使われることがほとんどない。それがない時に、それをぶる時やつける時になってようやく意味をあぶり出す。勿体とはそんな、もったいぶった用語なのである。
巡り歩けば巡り合う
「いい天気だなあ、どこかへ出掛けるか」とふと思った。大阪と接する京都府乙訓郡の大山崎は9月に訪れていたので、隣りの長岡京市へ行ってみることにした。仕事で何度か訪れている土地だが、駅周辺しか知らない。駅で地図を手に入れ、西山浄土宗の総本山、光明寺が紅葉狩りのスポットだと知り、バスを待つ人たちを横目に麓を目指して歩くことにした。
人混みもなく比較的静寂な境内で晩秋の景色を堪能した後、公園でカレーパンのランチ。帰りもバスに乗らずに歩くと決めた。歩くなら別ルートでと思い、住宅地の細道をジグザグと縫いながら乙訓寺と長岡天満宮に寄ってみようと歩き始めた。寺を目指して歩き始めて数分、ぼくより少し年配の夫婦らしき二人が三叉路の右手から歩いてきた。目と目が合った。
「こんにちは、どちらからですか?」とご主人が話しかけてきた。大阪と言ったものの、漠然としているので天満橋と言い足した。地名はご存知だった。「どちらに行かれるのですか?」と聞かれる。見知らぬ土地なのでキョロキョロと家並みや住所表示を見ていたから、迷い人として映ったのに違いない。「乙訓寺へ行ってみようと思っています」と答えた。
「家に帰るところで、ちょうどそっちの方向に行くところです」と言い、ご主人は案内人となって乙訓寺と弘法大師の話を語り始めた。ほどなく住宅地にある乙訓寺窯跡の前に出た。
話によると、奈良時代の8~9世紀に乙訓寺の瓦を焼くために作られた窯で、発見されたのは1966年とのこと。住居の土台部分が窯跡。何かの拍子に崩れたようだ。「ここは私の息子の家です。よろしければ先に向かいの方へどうぞ」と別の家を指差す。案内されたのはご主人の住居の裏庭。石や古木が所狭しと置かれ、柚子の木なども植わっている。
あまり他人の仕事を聞くことはないが、聞いてみた。雪舟筆法の水墨画家とおっしゃる。十代の頃に書道と絵画に少し打ち込んでいたので、話についていけた。向かいの窯跡の扉が開いたので中を見せてもらう。扉を開くと扉の裏側に、ご主人の手になる龍の絵が無造作に貼ってあった。
別れ際に自宅隣りの別邸の木からもぎたての檸檬と柚子をいただき、教えてもらった道順で乙訓寺と長岡天満宮に寄って帰路についた。一昨日、姉にこの話をした。父が篆刻をしていたのは知っているが、師匠の名前までは知らなかった……梅舒滴は初耳……その水墨画家に会ったとしても、私だったら「あ、そうですか」で終わってたなあ……と姉。父が篆刻を始めたのは姉が嫁いだ後だからやむをえない。
不案内な土地で特に当てのない巡り歩きをしていたら、少々縁のある人と話に巡り合って昔を偲んだというエピソード。