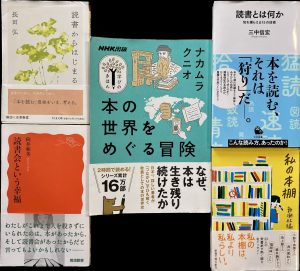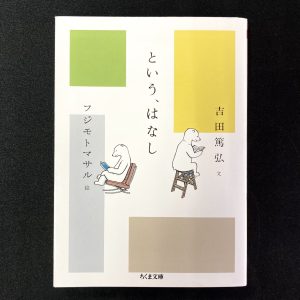わざわざ抜き書きするのだから賛意を表しているのだろうと、他人は思うらしい。そうとはかぎらない。賛意の場合もあるが、同意でもなく意を唱えるでもなく、よくわからないが、気になるので傍線を引くこともある。意見保留または感想放棄のままの抜き書きというところだ。今月はそんな3冊の本(3人の著者の本はそれぞれ10数冊、いや、それ以上本棚に並んでいる)。

一所から他所へ赴くのが「遊」の本義ならば、
一所にいて他所を徘徊するのもまた「遊び」である。
一所から他所へなら、たとえば「旅」がそうであり「引越し」や「転職」もそうだ。経験的にはたしかに「遊」だった。では、一所にいて他所を徘徊のほうはどうか。たとえば、今ここにいて他所を想像すれば遊び心が搔き立てられる。本業があって、それをベースにして、別の仕事をしてみるのも楽しい。
こんなふうにそのまま読めばいいのか、それとももう少し深読みするべきなのだろうか。この著者が書くのだから何か新しい「遊」なのだろうと期待するが、案外当たり前のことが書かれているのかもしれない。だからと言って、がっかりしているわけではないが……。

毎日少なくとも一回、何か小さなことを断念しなければ、毎日は下手に使われ、翌日も駄目になるおそれがある。
ニーチェのこのことばは難解である。「神は死んだ」よりも難解だ。著者の説明を元に、抜き書きの前段と後段を加えて再掲してみると次のようになる。
小さな自制心が欠如すると、大きな自制心も潰えてしまう。毎日少なくとも一回、何か小さなことを断念しなければ、毎日は下手に使われ、翌日も駄目になるおそれがある。自分自身の支配者となるよろこびを保持したければ、この体操は欠かせない。
体操とは「毎日一回、小さなことを断念すること」であり、自分自身の支配者とは「自分をコントロールすること」だろう。小さな欲望を捨てられないと、人生の大事な場面で自制心が利かなくなる……だから、毎日小さな欲望を捨てて、日々を上手に生きよう……そうすれば、自分を統御でき幸せになれる……と読み替えたがはたしてそれでいいのか。とは言え、毎日少なくとも一回、何か小さなことを断念できるほど、いろんな欲望を持ち合わせているわけではない。断念したくても断念するネタが先に尽きる。

老いるほどに人生は面白くなるという言い方は、確かに可能である。
肉体は衰える、知力も衰える、しかし、ひょっとしたら、魂が最も活発に活動するのはこの時期であるのかもしれない。
その歳まで、いったい何をしてきたのかと訝りたくなるような老人は多い。おそらく、何もしてこなかった。摂食、生殖、快楽の追求以外は何もしてこなかった。刺激に反応し、反応したら忘れるといった動物的生存の日々、そのような人々は、したがって老いることを拒む。
社会から老い始めたと見られる自分や同輩に照らし合わせると、おおむねその通りだと言える。ただ、魂の定義次第だが、肉体と知力が衰えたら魂も不活発になりそうな気がする。もし魂を精神と言い換えるなら、精神は知力に支えられるのではないか。
老いることを拒んで強引な策を凝らすのが加齢と闘う「アンチエイジング」、老いるペースに応じて生きる工夫をするのが加齢と融和する「スローエイジング」。意地や見栄を張る前者よりも、老いを素直に認めてしまう後者のほうがうんと楽である。
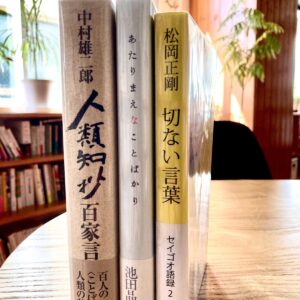
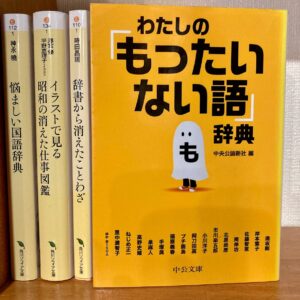
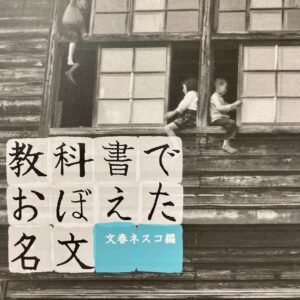
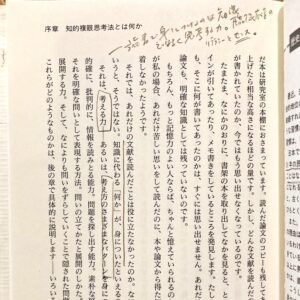
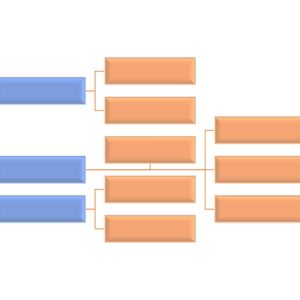
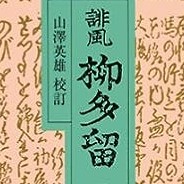
 二つ良いこと さて無いものよ 月が漏るなら 雨も漏る
二つ良いこと さて無いものよ 月が漏るなら 雨も漏る