岡倉天心は英語で『茶の本』を書いた。学生時代に読んだのは日本語版である。原文が英文だとはにわかに信じがたかった。後年英文で読んでもう一度驚いた。日本固有の概念や表現がものの見事にアルファベットで伝わってきたからである。新渡戸稲造の『武士道』にも鈴木大拙の『禅』にも同じ驚きを覚えた。いずれも日本語から英文への翻訳ではなく、原文が英語で書かれたのである。その『茶の本』に次の一節がある。
おのれに存する偉大なるものの小を感ずることのできない人は、他人に存する小なるものの偉大を見逃しがちである。一般の西洋人は、茶の湯を見て、東洋の珍奇、稚気をなしている千百の奇癖のまたの例に過ぎないと思って、袖の下で笑っているだろう。
自分は一流大学を卒業した、一流企業に勤めている、これこれのキャリアがある、何々分野の権威である、何よりも有名である……そう、自他ともに認める「偉大」なのだ。こう胸を張っても、それがいったいどれほどの意味を持つのか、と謙虚に問えるだろうか。偉大と言ってもたかが知れている、そんなものはちっぽけであると思えるか。自分の大は何があろうとも大であり、他人の小はどこまで行っても小であると見てしまうのが人の性。この習性は洋の東西を問わず、優位を感じている側に顕著に見られる。
ぼくたちはパリの国際度量衡局のメートル原器に基づいて定規やメジャーを作り、「同じ尺度」で長さを計測している。しかし、数値化不能なものや価値の認識のしかたや判断は人それぞれである。個人はそれぞれの尺度を持っている。だからこそ、同じ花を見て、ある者は美しいと感じ、別の者は美しいと感じない。これを一言化したのが、「人間は万物の尺度」(プロタゴラス)である。ここでの人間は個人というほどの意味だ。だからこそ、異論が生まれる。異論を無理に統一すれば人間の集合体の中で歪みが生まれる。もし一つにしなければならないのなら、話し合うしかない。これを議論とかディベートと呼んだのである。
企画を指導していていつも感じることがある。自分の企画したものを「これでいいのか、正しいのだろうか」と不安になる人たちが少なからずいる。彼らは「世間の尺度」、ひいては「偉い人や権威の尺度」が気になってしかたがない。そんな尺度で測られてたまるもんかという威勢のいい若者はめったにいないし、もしいたとしても、世間からは寸法違いだと見放されてしまう。
世界は偉人たちの水準で生きることはできない。
『金枝篇』を著わした社会人類学者ジェームズ・フレーザーのことばだ。こんな話をしながら随所で権威を引くとは複雑な気分である。ともあれ、世界にはいろんな人間がいる。千差万別の認識のしかたがある。偉人の尺度は参考にはさせてもらうけれど、呪縛されるわけにはいかない。ちっぽけかもしれないが、ぼくにはぼくの生き方、考え方、仕事の方法という都合があるのだ。


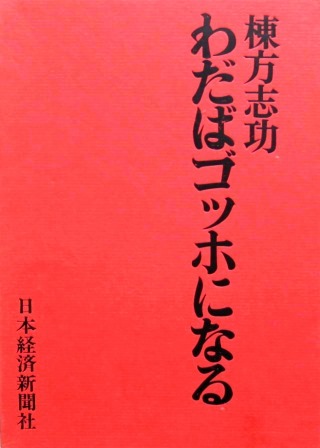





.jpg)
