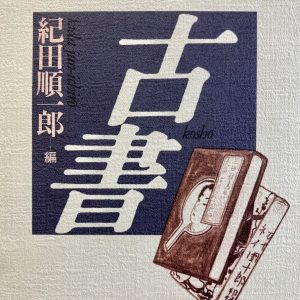「日本の名随筆」という古いシリーズがある。花、画、道などのテーマについて、錚々たる書き手が綴った文を編集したものだ。全部揃えると120巻になるので、古本屋に出ていたら気に入ったテーマのものだけ買って読んできた。『古書』は別巻20冊のうちの一冊。
古書の売買や収集には、新刊書ではありえないようなエピソードがつきまとう。本書の随筆の一編、松永伍一の『巴里の掘出し物』では苦労して稀覯本を手に入れる話がいろいろ書かれている。セーヌ河畔に出る古本屋台では、なんとレンブラントの銅版画が一枚1,500円ほどで売られていた。著者は意気揚々として18枚を掘り出した。
古書店を営んでいる皆がみな目利きとはかぎらない。レンブラントがどんな画家で作品にどのくらいの値がつくかなど知らず、本や書画を1,000円で手に入れたら1,500円で売って500円儲ければ良しと考える古物商もいる。老舗の、特に日本の古書店では、勘違いでもしないかぎりこんなことはほとんどありえない。チェーン店のBOOK・OFFではたまに初版本の掘出し物が出ていることがある。
同書の『古本綺譚』では月下氷人になった一冊の古本が紹介されている。九州の女性が『君たちはどう生きるか』という本を読み、愛読者ハガキに記入した。ところが、そのハガキを投函するのを忘れて、本の間に挟んだまま後日近所の古本屋に売り払った。その本が回りまわって東京の古本屋で売られ、それをある男性が買った。愛読者ハガキには住所氏名が書いてある。男性が手紙を書き女性が返事を出す。文通が一年続き、二人は結婚した。
この話から20年前の映画『セレンディピティ(serendipity)』を思い出した。「想像外の偶然や発見」のことをセレンディピティと言うが、この映画の題名でそのことばを初めて知った。少々ネタバレになるが、ざっと次のような話である。
クリスマス前のデパートで男女が偶然出会う。お互い惹かれるのだが、それぞれに恋人がいる。もし二人の出会いが運命ならいつかまた会えると考え、女のほうは持っていた古本に、男のほうは5ドル札にそれぞれの連絡先を書く。古本を手放し、5ドル札は買物に使う。数年後、二人はお互いを探し始め、何度もすれ違いを繰り返しながら、ついに男が女の連絡先を書いた古本に出合う。しばらくして、女も男が連絡先を書いた5ドル紙幣に出合う。
アメリカらしい「とんでもストーリー」だ。広い全米で五万と流通する5ドル紙幣の中からたった一枚の札に巡り合うのは不可能だ。セレンディピティの小道具としてはかなり無理がある。しかし、古本なら、それが稀覯本であったり骨董価値が高かったりすると、流通範囲が限られてくるので、自分が売った本を買い戻せるチャンスはゼロではない。
狙いをつけて買った古本がつまらなくて途中で投げ出し、百円均一コーナーからついでに買った古本に夢中になるということはよくある。本命でないところに望外の価値を偶然見つけることもセレンディピティ。もっと言えば、気まぐれに店に立ち寄り、直感だけで手に取って買って読む古本のことごとくがセレンディピティの成せる読書の縁に思えてくる。