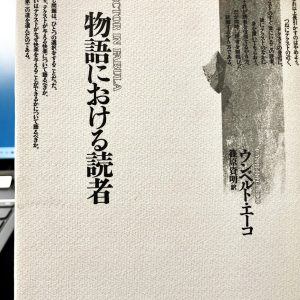いきなりで恐縮だが、少々長い下記の引用文をお読みいただきたい。
一九六二年に『開かれた作品』を出版したとき、私は、どのようにして芸術作品が、一方で、その受信者の側に解釈による自由な参加を要請しながらも、他方で、その解釈の次元を刺激すると同時に統制する構造特性を提示するのかと、自問した。もっと後で知ったのだが、当時私はテクストの実用論を、そうと知らないまま実践していた。いや少なくとも、今日のいわゆるテクストの実用論のひとつの側面、つまり共同作業行為に取り組んでいたわけだ。受信者はこの行為によって、テクストが語らないもの(前提し、約束し、含意し、ほのめかすもの)をテクストから引き出し、空所を埋めるよう仕向けられるのであり、またこの行為こそが、テクストに存在するものをテクスト相互性の織物へと連結するよう仕向けるのである。当のテクストがそこから生まれ、そこへと合流していくテクスト相互性の織物へと。共同作業の動き、のちにバルトが示してくれたように、これこそがテクストの快楽を、そして――特権的な場合には――テクストの悦楽を生みだすものなのだ。
引用は、ウンベルト・エーコの『物語における読者』の序文の第一段落。序の序からしてこの難解さ。と言うか、判読不能の極み。書かれているテクストに読解力が及ばないせいか、イタリア語からの翻訳に問題があるせいかはわからない。これは古本屋で500円ほどで買った一冊だが、すでに数ヵ所に付箋紙が貼ってあった。この本の前の所有者が最初から最後まで読んだのかざっと見ただけなのか、これまたわからないが、付箋紙が貼れたのだから、ぼくの判読能力よりも上と思われる。
文章の判読性が低いと、読者に意味がすっと伝わってこない。しかし、読者がそこに書かれている事柄をある程度読み解く知識があれば、読み続けることができる。古本屋で買うのをためらわず、今ぼくの手元にこの本があるという事実、長編小説『薔薇の名前』で名の知れた著者のウンベルト・エーコはすでに何冊か読んでおり、「テクスト」というテーマにも関心があるという事実を踏まえると、ぼくはこの一冊をある程度読めなければいけないはずである。しかし、さっぱりわからないのだ。
これほどさっぱりわからない読書はかなり久しぶり、と言うか、初めてのことかもしれない。「さあ、ここまで上がってこれるかい? 悪いけれど、こっちからきみの所へは下りていくつもりはない。この本で引用している実在の人物や彼らの著書について、きみが承知しているという前提でこの本を書いた。妥協は一切していない……」。ページをめくりながら、そんなエーコの(あるいは翻訳者の)つぶやきが聞こえてきた。
意味がよくわからないまま本を読み続けることができるかと問われれば、できそうもないと答える。しかし思い起こせば、学生時代に哲学や経済の翻訳書を何冊も読まされた経験がある。何もわからずに読んだふりをした記憶もある。今はどうか。脳はただ朦朧とし目は虚ろに文面を追っている。先週の水曜日から土曜日まで仕事に追われていた。一段落して読書でもと思って手にした本を間違ってしまったようである。
あちこちのページを飛び石伝いに眺めてきて、次の『7 予想と推考散策』という章の冒頭を最後に本を閉じた。
7・1 蓋然性の離接
それをとおして読者がファーブラを顕在化するマクロ命題は、恣意的な決定に依拠するのではない。それらの命題は、テクストが担うファーブラをほとんど顕在化するはずなのだ。生産されたかぎりでのテクストに対するこの「忠実性」の保証は、経験的なテストをとおしても検証できる意味論的な諸規則によって与えられる。(……)
ファーブラがわからない。最後の「テスト」が正しいのかテクストの誤植かどうかすらわからない。ここに到って、声なき笑いが込み上げてきた。わからなさすぎると読者は、パニックに陥るのではなく、諦観するかのように笑う。ある程度読めるが一部だけわからない人は苦しむが、さっぱりわからずに読み続ける人は判読不能の快さを感じ始める。エーコの言う「テクストの悦楽」が生まれてくるのだ。一度目よりも二度目、二度目よりも三度目と、読書の悦楽は増幅する。ぜひ試していただきたい。