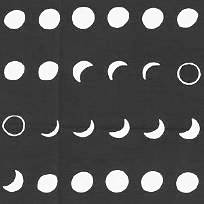中高生の頃に付箋を使った記憶はない。その頃までに付箋は存在していたはずである。しかし、縁がなかった。付箋ということばの前にポストイットを知った。社会人になってからの話。使い始めの頃はポストイットと呼んでいたが、今では付箋と言う。
糊付きの付箋しか知らないが、おそらく昔はしおりと同じ使い方をしていたに違いない。読書家や学者らは自前で小さな紙片を作り、本に挟む際にテープで貼ったり糊付けしたりして使ったようだ。裏に糊を付けたことで近年の付箋はスグレモノになった。しかし、貼ったのはいいが、剥がせないと困る。ポストイットが画期的だったのはさっと貼って無理なく剥がせるという点。この脱着可能なゆるい糊が失敗の産物だったというのは有名な話だ。
再読するために今読んでいる本の箇所をマークするには二つの方法がある。傍線を引くことと付箋を貼ることである。前者の問題は、本の外から即座に傍線箇所を見つけにくいこと。かなりページを繰らなくてはいけない。本も汚れる。付箋なら本は汚れないが、一つ問題がある。ページのどの行を参照したいのか一目でわからないのだ。結局、傍線と併用することになる。
本を読んでいると何かに気づく。ハッとする行があれば傍線を引く。文章が一行か二行なら傍線でいい。しかし、マークしたい箇所が数行に及ぶ時は付箋が便利である。自分が書いた文章を読み直していて気づき、書き足すこともある。だから、ぼくは自分のノートにも付箋を貼っている。但し、付箋の貼り過ぎには注意。目印効果がなくなるからだ。
一年前にしたためたノートの雑文。書き直してブログに転載しようと思った。読み直しながらいろいろ考えてまとまりかけた時、一本の電話が鳴った。ちなみに、ぼくが使っているノートはバイブルサイズのシステム手帳。リフィルにびっしりと書き込んでいる。随時別のバインダーに移し替えるが、常時500枚は綴じてある。
別に閉じることなく電話に応じればよかったのに、反射的に閉じてしまった。電話を切った後、そのページに戻ろうとした。だいたいこのあたりと見当をつけて前後のページの表裏を丹念に目配りするも、見つからない。ほぼ全ページを丁寧に一枚ずつ捲ってやっと見つけたという次第。ロスした時間は約10分。
読書中も参照中も付箋貼りはマメでなければならない。ところが、反省してマメに貼ろうとすれば、今度は付箋が手元になかったりする。食事処なら箸袋やナプキンを挟む。挟んだその本を鞄に入れて帰宅。本を取り出したら箸袋やナプキンが滑り落ちてページを見失う。つくづくポストイットのありがたさを実感する瞬間である。