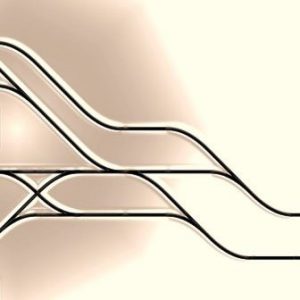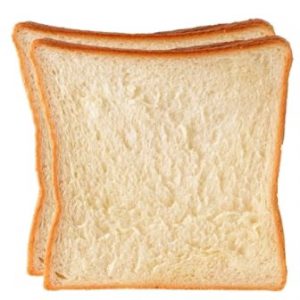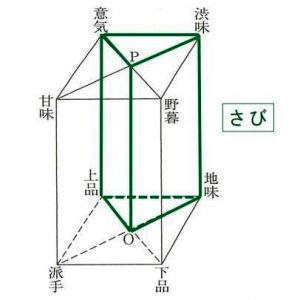防災ニュースで天気予報をチェックする。今日の熱中症情報欄には〔危険〕とある。午後2時現在、35℃。オフィスのベランダに出ると、微風が外気の熱とエアコンの室外機の熱をミックスして運び、酸欠の罠を仕掛けている。
午後3時のコーヒーのつもりが、フライングして午後2時に淹れた。豆はインドプランテーション。雑味なくさっぱりとしている分、眠気払いの効果はどうだろう。最近復活したぶどう糖のタブレットを口に含み、コーヒーを啜る。
今日はゆったりペースだが、先週は仕事の後にもう一仕事が控えていて、午後3時からも闘っていた。闘いの武器はコーヒーとぶどう糖。時折り、オフィスの外に出てワンブロックほど歩いて戻ってくる。暑さの逆療法という息抜きだが、今日これをすると危険である。
ところで、いま「闘い」と書いたが、仕事と闘っているわけではない。仕事は生業であり食い扶持であるから、闘うべき敵どころか、心強い味方のはずだ。存在しないゴドーを待てないように、存在しない敵に立ち向かうことはできない。そもそもはっきりと勝ち負けの決着がつくような仕事をしているつもりもない。
今月、訃報が二件届いた。享年65歳と63歳。二人を含めると、この一年半で60代の友人知人が7人も逝ってしまった。これはちょっと尋常ではない。平均寿命が延びて、周囲には80代後半から90代が少なからずいる。その一方で、ここ数年、50代、60代の訃報も届く。
ホモサピエンス的な遠大なスケールで眺望すれば、歴史は始まり、そしていつか終わる。しかし、個人の歴史の終焉は同時代人として確認できてしまう。どなたも遣り残したこと多々あるに違いない。遣り残しはやむをえない。一人の人生で何もかもできないからだ。しかし、可能なら、考え残しはなるべく少なくしておきたい。元気なうちに、他人の死を通じて、人間を、人生をもうちょっと考えておくべきだと思う。
感傷的に七月を終えるつもりはない。読もうと思って放置していた本を引っ張り出して傍らに置き、それでもページを繰ることもなく、インドプランテーションを味わう。味わえるという、ただそれだけのことで、熱気で間延びしかけていた時間と空間がほんのちょっぴり引き締まった。